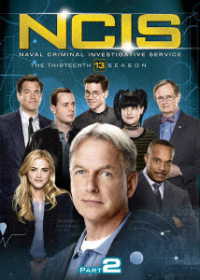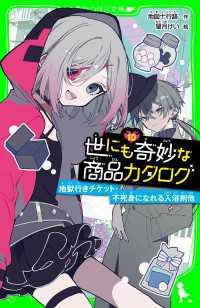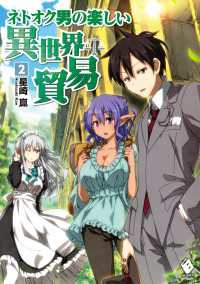出版社内容情報
つぶやき、うめき声、赤ん坊の訴え。言葉になる以前の場所に、音楽と詩と政治の起源がある。哲学と言語の存在する根拠を示す必読書。本書は「哲学とはなにか」という問いに、「音声」「要請」「言い表しうるもの」「序文」「ムーサ(詩歌女神)たち」をテーマにした五つのテクストをつうじて答えている。人間の言語活動の始原にあるもの、その根本的な構造、音声と言語の差異を追って、考古学的研究と理論的研究が密接にからまりあう。
音声と言葉、音と意味が接触する瞬間を思考と呼ぶなら、詩と哲学は互いのなかに内在している。哲学とは音声を探究し記憶にとどめる行為のことだ。詩が言語を愛し、探究する行為であるのと同じである。
西洋の知は、究極的には、奪い去られた音声、文字への転写を基礎として構築されてきた。これこそは、西洋の知の脆弱な、しかしまた強靭な創建神話である。それらの延長線上に、現実を救うことを放棄して破壊に向かう科学と、もはや挑戦をせず、感性界とのつながりを失った哲学がある。
世界への原初的な開かれは論理的なものではなくて、音楽的なものだ。詩歌女神(ムーサ)たちの住まう場所。よって哲学は今日、音楽の改革としてのみ生じうる。
「哲学者が書いているすべてのことは、書かれていない作品への序文である」──かつて予告した「人間の声」をめぐる構想に、アガンベンは25年をへて取り組んだ。
まえおき
音声の経験
要請の概念について
言い表しうるものとイデアについて
序文を書くことについて
付録 詩歌女神(ムーサ)の至芸――音楽と政治
訳者あとがき
文献
人名索引
ジョルジョ・アガンベン[ジョルジョ アガンベン]
1942年ローマ生まれ。ヴェネツィア建築大学教授を務めたのち、現在はズヴィッツェラ・イタリアーナ大学メンドリジオ建築アカデミーで教えている。主要著書に《ホモ・サケル》シリーズのほか、『中味のない人間』(1970)『スタンツェ』(1977)『幼児期と歴史』(1980)『言葉と死』(1982)『到来する共同体』(1990)『目的なき手段』(邦訳『人権のかなたに』1995)『残りの時』(2000)『涜神』(2005)『イタリア的カテゴリー』(2010)など。
上村忠男[ウエムラタダオ]
1941年兵庫県尼崎市に生まれる。1968年、東京大学大学院社会学研究科(国際関係論)修士課程修了。東京外国語大学名誉教授。学問論・思想史専攻。
内容説明
音声を奪われて文字と化した知の弱さ、無調律の政治風景。哲学は今日、音楽の改革としてのみ生じうる。言葉の始原=詩歌女神たちの場所へと、思考を開く。
目次
音声の経験
要請の概念について
言い表しうるものとイデアについて
序文を書くことについて
付録 詩歌女神の至芸―音楽と政治
著者等紹介
アガンベン,ジョルジョ[アガンベン,ジョルジョ] [Agamben,Giorgio]
1942年ローマ生まれ。ヴェネツィア建築大学教授を務めたのち、現在はズヴィッツェラ・イタリアーナ大学メンドリジオ建築アカデミーで教えている
上村忠男[ウエムラタダオ]
1941年兵庫県尼崎市生まれ。東京大学大学院社会学研究科(国際関係論)修士課程修了。東京外国語大学名誉教授。学問論・思想史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
34
読書の鬼-ヤンマくん
Matsumouchakun