出版社内容情報
誰もが詩を書き、ガリ版を刷り、集まっては批評しあった。50年代の東京で活躍した「下丸子文化集団」から見える、もう一つの戦後史敗戦後の1950年代、「サークル文化運動」が空前の盛り上がりをみせていた。誰もが詩や小説を書き、それを印刷し、集まっては批評しあった。文化産業は未発達で、そして人々は貧しかった。サークル文化運動は若い工場労働者の間でまたたくまに広まり、文学サークル、うたごえサークル、演劇サークルなど、全国各地に無数のサークルができた。
そのなかでも光を放っていたのが、東京南部の「下丸子文化集団」である。多くの工場や軍需工場がひしめく一大工業地帯だった東京南部(大田区・品川区・港区)で働く若い労働者による「下丸子文化集団」は、『詩集 下丸子』『石ツブテ』などの冊子や、「原爆を許すまじ」などの歌を生み出し、全国に大きな影響を与えた。
当時のサークル文化運動は左翼文化の影響を強く受けており、労働者たちは共産党や労働組合との緊張関係のなかで、時には党の方針に翻弄されながら、生き生きとした表現をつくりだし、やがては思想的に自立することになる。
わら半紙にガリ版の印刷物、うたごえ運動や演劇活動ゆえに、一大ブームを巻き起こしたサークル文化運動は、資料としてわずかな痕跡しか残していない。本書はそれらの資料の丹念な読み込みと、当事者への膨大なインタビューを行いながら、「もうひとつの戦後史」を鮮やかに浮かび上がらせる。
はじめに
第一章 工場街に詩があった
第二章 下丸子文化集団とその時代
第三章 無数の「解放区」が作り出したもうひとつの地図
補章 サークル運動の記憶と資料はいかに伝えられたか
第四章 全国誌と地域サークル
第五章 東京南部における創作歌運動
第六章 工作者・江島寛
第七章 東京南部から東アジアを想像した工作者
註
東京南部文化運動年表
あとがき
道場親信[ミチバチカノブ]
1967年生まれ。和光大学現代人間学部教授。専門は社会運動論・日本社会科学史。著書に『占領と平和――〈戦後〉という経験』(2005年、青土社)、『抵抗の同時代史――軍事化とネオリベラリズムに抗して』(2008年、人文書院)、『下丸子文化集団とその時代――一九五〇年代サークル文化運動の光芒』(2016年、みすず書房)。共著に『社会運動の社会学』(2004年、有斐閣)、『戦後日本スタディーズ 2』(2009年、紀伊國屋書店)、『読む人・書く人・編集する人――『思想の科学』50年と、それから』(2010年、思想の科学社)、『〈つながる/つながらない〉の社会学――個人化する時代のコミュニティのかたち』(2014年、弘文堂)、『ひとびとの精神史』第2巻・第6巻(2015年、岩波書店)、『岩波講座 日本歴史』第19巻(2015年、岩波書店)ほか。
内容説明
誰もが詩を書き、ガリ版を刷り、集まっては語りあった。1950年代、軍需工場ひしめく東京南部で活躍した「下丸子文化集団」から鮮やかに浮かび上がる、もう一つの戦後史。
目次
第1章 工場街に詩があった
第2章 下丸子文化集団とその時代―五〇年代東京南部サークル運動研究序説
第3章 無数の「解放区」が作り出したもうひとつの地図―東京南部の「工作者」たち
補章 サークル運動の記憶と資料はいかに伝えられたか
第4章 全国誌と地域サークル―東京南部から見た『人民文学』
第5章 東京南部における創作歌運動―「原爆を許すまじ」と「南部作詞作曲の会」
第6章 工作者・江島寛
第7章 東京南部から東アジアを想像した工作者―江島寛再論
著者等紹介
道場親信[ミチバチカノブ]
1967年生まれ。和光大学現代人間学部教授。専門は社会運動論・日本社会科学史。2016年9月逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ポカホンタス
古戸圭一朗
takao
tkm66
Hisashi Tokunaga
-
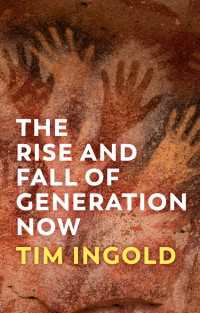
- 洋書電子書籍
- T.インゴルド『世代とは何か』(原書)…
-

- 洋書電子書籍
-
人工知能の時代:予測・問題・多様性
-
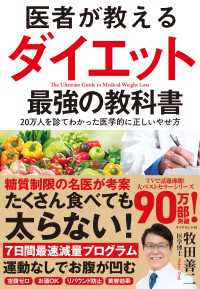
- 電子書籍
- 医者が教えるダイエット 最強の教科書 …
-

- 電子書籍
- タンデムスタイル2019年9月号





