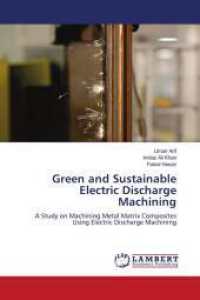出版社内容情報
精神分析界に根づく伝統的概念を豊富な臨床経験を通して再考し、ときに描きなおすことによって生まれる、新しい時代の精神分析入門。フロイトが精神分析を創始してから100年以上の時がすぎ、行動科学に基づいた心理療法が盛んになったいま、精神分析はもはや「過去の遺物」なのだろうか?
著者はクライエント中心療法の訓練を受けて心理療法家としての道を歩みはじめ、精神分析を学び、さらにアタッチメント理論に基づく心理療法へと活躍の場を広げてきた。本書は、長年にわたり多様なスタイルで心理療法を行ってきた著者が、精神分析がいかに心の理解に役立つのかを詳説するものである。
飛躍的に進歩する発達理論、実証研究の不足、男性中心主義の限界……。伝統的な精神分析の考え方を豊富な臨床経験を基に再考し、ときに不要なものは切り捨て、描きなおしてゆく。精神分析理論を細部まで再点検していく筆致は、これまで精神分析を敬遠してきた臨床家にも理解しやすく、心への新たな接近法を示すだろう。
心の専門家に本当に必要なものとは何か。精神分析理論を見つめる著者のまなざしは、心という形なきものを探求しつづける心理療法家としての矜持に満ちている。
第1章 精神分析学の発展と批判
1 フロイトの生涯
2 フロイトとユングとシュピールライン
3 精神分析学の展開――限界と可能性
4 精神分析理論の否定による理論展開
第2章 心の構造と機能
1 はじめに
2 エス
3 自我
4 超自我
第3章 精神分析的に見る人間の発達
1 E・H・エリクソンの貢献と限界
2 男性中心主義への批判
第4章 心理療法における見立てと精神分析
1 心理療法における二つのモデル
2 クライエントにとって信頼できる治療者――クライエント中心療法とアタッチメント理論の視点から
3 クライエント個人が抱える問題の見立てと精神分析
4 治療者の限界の見立て
5 身体に刻まれた歴史
6 無意識による無意識の理解――転移と逆転移
7 家族史について
8 対人関係についての見立て――同一化対象とアタッチメント対象
9 社会的文脈における見立て
第5章 心理療法の営みと精神分析
1 自由を得る営みとしての心理療法
2 転移‐逆転移関係と治療空間の閉鎖性
3 心理療法における「転移現象」の視点の有効性
4 無意識へのアプローチとしての言葉とイメージ
5 無意識へのアプローチとしての夢分析
6 無意識と象徴
7 人格変化と現実適応
8 治療者の不自由さ
9 治療者を自由にする道具としての理論――アタッチメントと精神分析
おわりに
文献
索引
林もも子[ハヤシモモコ]
1960年生まれ。1983年東京大学文学部心理学科卒。1991年東京大学教育学研究科博士課程単位取得退学。立教大学現代心理学部教授。臨床心理士。ASIコンサルタント。著書に『思春期とアタッチメント』(みすず書房 2010)『精神分析再考』(みすず書房 2017)、共著書に『人間関係の生涯発達心理学』(丸善出版 2014)『甘えとアタッチメント』(遠見書房 2012)『アタッチメントと臨床領域』(ミネルヴァ書房 2007)『思春期臨床の考え方・すすめ方』(金剛出版 2007)『臨床心理学研究の技法』(福村出版 2000)『心理療法のできることできないこと』(日本評論社 1999)などがある。
内容説明
精神分析はいま、どう理解し、心理療法の現場でどのように用いていけばよいのだろうか?実証研究の不足、男性中心主義の限界…豊富な臨床経験から“伝統”を再考し、精神分析を描きなおす。
目次
第1章 精神分析学の発展と批判(フロイトの生涯;フロイトとユングとシュピールライン ほか)
第2章 心の構造と機能(エス;自我 ほか)
第3章 精神分析的に見る人間の発達(E.H.エリクソンの貢献と限界;男性中心主義への批判)
第4章 心理療法における見立てと精神分析(心理療法における二つのモデル;クライエントにとって信頼できる治療者―クライエント中心療法とアタッチメント理論の視点から ほか)
第5章 心理療法の営みと精神分析(自由を得る営みとしての心理療法;転移‐逆転移関係と治療空間の閉鎖性 ほか)
著者等紹介
林もも子[ハヤシモモコ]
1960年生まれ。1983年東京大学文学部心理学科卒。1991年東京大学教育学研究科博士課程単位取得退学。立教大学現代心理学部教授。臨床心理士。ASIコンサルタント(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
-

- 洋書
- Love Unbound