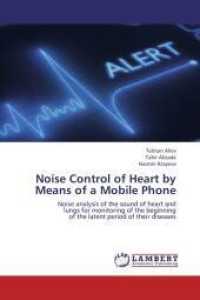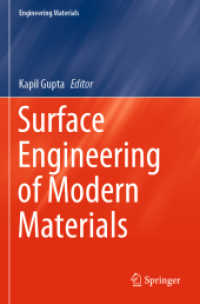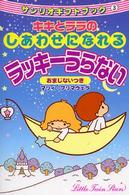- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 日本の哲学・思想(戦後思想)
出版社内容情報
戦後を代表する「思想史家」の誕生を告げた画期的デビュー作を新シリーズで。国家とムラ社会をつなぐ装置としての天皇制とは何か。
内容説明
「教育勅語は典型的近代国家の法に代るべき天皇制国家の法なのである」―戦後を代表する「思想史家」の誕生を告げた、朽ちることなき論考。鮮烈なデビュー作。
目次
天皇制とは何か
天皇制国家の支配原理
天皇制とファシズム
天皇制のファシズム化とその論理構造
「諒闇」の社会的構造―「昭和元年」の新聞から
付録(書評 石田雄著『明治政治思想史研究』;日本における組織方法論について―地方青年団体をモデルにして)
著者等紹介
藤田省三[フジタショウゾウ]
1927‐2003。思想史・精神史。愛媛県に生まれる。1953年東京大学法学部政治学科卒業。以後、中断をはさんで1993年3月まで法政大学勤務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
林克也
4
いいなあ、この本。読んでよかった。一つ一つの文章や言葉使いは難解だが、文章全体から立ち上る“異議申立て”と、自由な精神への叫び。惰性で生きる人、思考しないことを得意とする人が読むにはハードルは高いが、今の日本(人)の成り立ちを理解するための重要な論文の一つだと思う。多くの若い人が読んで刺激を受けるといいのだが・・・・・・。2016/01/28
KAZOO
4
日本の近代政治思想史を志そうという人にとっては必読の文献であると思います。四つの論文がありますが、やはりこの本の題名となっている論文が中心を占めています。著者のあとがきにもあるように本当は明治末期までを書きたかったようなのですが、明治維新前後を中心とした第1章のみで終わっています。しかしながらその論点は非常に鋭く、これだけの短い論文ではありますが、読み応えがあり、最近の政治学者ももう少し勉強してもらいたいと感じました。丸山真男の「超国家主義の論理と心理」と一緒に読むといいと思います。2013/01/20
kotsarf8
4
そういえばちょうど読み終わったのが天皇誕生日だったのね(笑) 日本では強力な近代国家権力を樹立するに当たって、依拠すべき強力な正当化装置がなかったこと、その苦肉の解決策が天皇制だったことが分析されている。権力の基盤がが弱いからこそ強力な教化、心情的権威(それは破綻を宿命づけれれているのだが)を必要としたということ。強化冒頭の表題作は難解なので、後のほうから逆順に読み進めていくと良いでしょう。2012/12/23
浅井秀和 「不正規」労働者
2
明治大正の日本臣民が君が代はあくまで「皇室の歌」であって国歌ではない、という共通認識だった、というのを当時の大阪朝日新聞を紹介して述べていることを知って愉快なり2013/12/23
メルセ・ひすい
2
第一版は、『天皇制のファシズム化とその論理構造』…そのままであるが、但し!「戦争体験」という語の「体験」という単語を「経験」に、「挫折」という単語を「失敗」に直した。この二語だけは嫌いだ。戦後を代表する思想史家・藤田省三が、天皇制国家の辿った歴史過程の複雑かつ錯綜した文脈が含む論理過程の重層的な構造分析により、きわめてラディカルに戦後を代表する思想史家・藤田省三が、天皇制国家の辿った歴史過程の複雑かつ錯綜した文脈が含む論理過程の重層的な構造分析により、きわめてラディカルに「天皇制国家」克服への道を示す。2013/01/05
-

- 和書
- 魚類発生学の基礎