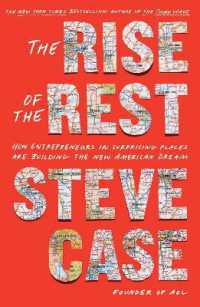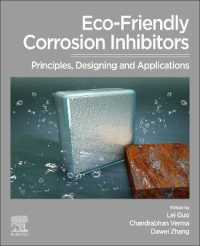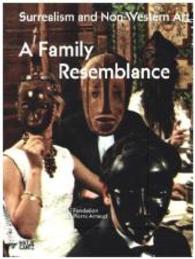- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 構造主義・ポスト構造主義
出版社内容情報
1966年5月にはじめて日本を訪れたバルトは、それから2年たらずのあいだに三か月間も日本で過ごした。そこでの幸福感と解放感は、バルト自身の知的風景や活動を一変させてしまう。そこで口をついて出た「身体」「断章(フラグマン)」「ロマネスク」という概念は1970年代を通してバルトにとって重要なものとなる。本書は、この日本体験から生まれ、これまで『表徴の帝国』として読まれてきた名著の、30年ぶり、まったく新しいみごとな翻訳である。このたび、スキラ社版オリジナルの構成を尊重して、カラー図版をそのままに、テクストと写真の交錯を体験できるようにした。訳者による精密な解説「俳句に誘われて――断章と写真と小説」を巻末に付している。
-------------------------------
ロラン・バルト著作集 全10巻
既刊 1 文学のユートピア
3 現代社会の神話
7 記号の国
10 新たな生のほうへ
--------------------------------
ロラン・バルト(Roland Barthes)
1915年生まれ。フランスの批評家・思想家。1953年に『零度のエクリチュール』を出版して以来、現代思想にかぎりない影響を与えつづけた。1975年に彼自身が分類した位相によれば、(1)サルトル、マルクス、ブレヒトの読解をつうじて生まれた演劇論、『現代社会の神話(ミトロジー)』(2)ソシュールの読解をつうじて生まれた『記号学の原理』『モードの体系』(3)ソレルス、クリテヴァ、デリダ、ラカンの読解をつうじて生まれた『S/Z』『サド、フーリエ、ロヨラ』『記号の国』(4)ニーチェの読解をつうじて生まれた『テクストの快楽』『彼自身によるロラン・バルト』などの著作がある。そして『恋愛のディスクール・断章』『明るい部屋』を出版したが、その直後、1980年2月25日に交通事故に遭い、3月26日に亡くなった。バルトの単行本はすべて、みすず書房から刊行される。
石川美子(いしかわ・よしこ)
1980年、京都大学文学部卒業。東京大学人文科学研究科博士課程を経て、1992年、パリ第VII大学で博士号取得。フランス文学専攻。現在、明治学院大学教授。著書『自伝の時間――ひとはなぜ自伝を書くのか』(中央公論社)『旅のエクリチュール』(白水社)ほか。訳書 モディアノ『サーカスが通る』(集英社)フェーヴル『ミシュレとルネサンス』(藤原書店)『新たな生のほうへ』(ロラン・バルト著作集10、みすず書房)ほか。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
あなた
ラウリスタ~
メルセ・ひすい
横丁の隠居