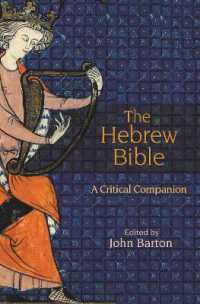- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 日本の哲学・思想一般(事典・概論)
出版社内容情報
徳川時代、慢性的な飢饉のなかで民衆は緊急時のために、互助組織「講」を発展させた。海保青陵、二宮尊徳など、優秀な指導者がいた。
徳川時代、慢性的な飢饉のなかで民衆は、緊急時のための相互扶助の組織、「講」を発展させた。海保青陵、二宮尊徳をはじめ、優秀な商人指導者たちがいた。厳しい身分制度の下で、かれらは倫理意識が強く、経済活動にも誇りをもっていた。各地でさまざまな「講」が発展し、その名残は今も見られる―「相互銀行」「共済保険」。著者はその詳細をたんねんに掘り起こし、近代が率先して忘れ去った民衆の知恵を、驚きとともに発見する。
日本の読者へ/まえがき/第一章 徳の諸相/第二章 常識としての知識/第三章 組織原理としての講/第四章 倫理の実践としての労働/第五章 報徳と国家の近代化/第六章 無尽会社/終 章 断片的な論考/解説/原注/参考文献/索引
内容説明
飢饉に苦しんだ徳川時代の民衆の実践。その伝統は公の歴史の陰で地道に生き続け、震災のボランティア活動につながる。卓越した歴史家の観察眼と想像力の結晶。
目次
第1章 徳の諸相
第2章 常識としての知識
第3章 組織原理としての講
第4章 倫理の実践としての労働
第5章 報徳と国家の近代化
第6章 無尽会社
終章 断片的な言説
著者等紹介
テツオ・ナジタ[テツオナジタ]
ハワイ生まれ。1965年、ハーヴァード大学で博士号取得。カールトン・カレッジ、ウィスコンシン州立大学を経て、1969年以降シカゴ大学で教鞭をとる。現在、シカゴ大学名誉教授、ロバート・S・インガソル記念殊勲教授(歴史学・東アジア言語文明研究)。専攻は近代日本政治史・政治思想史。1989年に大阪府より山片蟠桃賞を受賞
五十嵐暁郎[イガラシアキオ]
1976年、東京教育大学大学院文学研究科博士課程修了。1987‐2012年、立教大学法学部教授。現在、立教大学名誉教授。専攻は現代日本政治論
福井昌子[フクイショウコ]
立教大学卒業。企業勤務、英国留学を経て、現在、翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
1.3manen
funuu
takao
Ven・The・Block