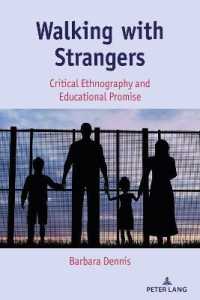出版社内容情報
生殖技術は社会をどう変えるのか。卵子・精子の商品化、代理母、再生医療との関係など、生殖技術がもたらす問題を立体的に考察する。
内容説明
生殖技術は社会をどう変えるのか。社会は技術に何を期待するのか。不妊治療の範囲をはるかに越えて発展する生殖技術の問題と解決を照らし出す、画期的論考。
目次
第1章 卵子・胚・胎児の資源化―何が起きようとしているのか
第2章 生殖技術と商品化―精子・卵子の売買、代理出産をめぐって
第3章 先端技術が「受容」されるとき―再生医療研究の事例から
第4章 再生医療の「倫理」問題
第5章 生殖技術と女性の身体のあいだ
第6章 生殖補助医療から見る日本の家族観―AIDをめぐる政治・倫理・社会
第7章 卵子を提供する行為を考える―利他と利己
第8章 生殖における女性の自己決定権―半世紀の議論の成熟と課題
第9章 医師の論理と患者の論理―医療化した生殖と価値
著者等紹介
柘植あづみ[ツゲアズミ]
1960年生まれ。埼玉大学大学院理学研究科生体制御学博士前期課程修了。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程満期退学。お茶の水女子大学より博士(学術)授与。現在、明治学院大学社会学部教授。専攻は医療人類学、生命倫理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
3
ふむ2022/01/12
たろーたん
1
本筋ではないのだが、「中絶による死亡胎児を利用することの是非」が印象に残った。これは空想の話ではなく、アメリカの国立衛生研究所は、1990年代末に、専門家や市民団体にヒアリングし、「胎児組織が廃棄物と見做されており、そのため母親の同意なしで研究に使われていた」ことが明らかになったらしい。ちなみに、日本は、例えば、中絶による死亡胎児の卵巣から得られる卵子から作られる特殊な培養細胞(EG細胞)の利用の是非など議論はあったようだが調査はされていないみたい。2024/06/10
かなで
1
卒論関係。いろいろ興味深い。感想を書くのを忘れていたし、もう一回さらっと読んで感想を後で足す。/32冊目2020/10/27
vonnel_g
0
五体満足な子どもが産めるのは健康のしるし、と思われているけれどそれは本当なのか。不妊の状態が何故「治療」されねばならないのか。妊娠出産は単に子どもを持つ以上の社会的・文化的な意味を負わされており、それで追いつめられる人たちがたくさんいる。選択の良い悪いを決めるのは誰なのか、誰かの選択がその人にとってのベストになるようにしていくにはどうすれば良いのか。大変に難しいけれどみんなで、それぞれで向き合って行ければと思う。2015/08/17
産廃屋
0
不妊治療を受けることの積極面よりも、スティグマとしての不妊を否定せんがための消極的なものと考えているのが垣間見えるのが難点。 今年あたりから着床前診断が行われるようになり、不妊治療は保険診療になる方向で進んでいる。状況は劇的に変わりつつある。 新しい情報を織り込んだ類書を読みたい。2019/08/11