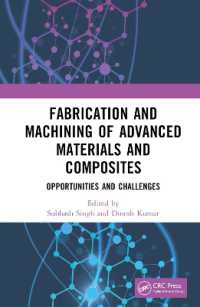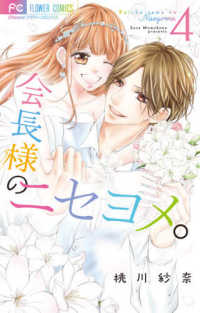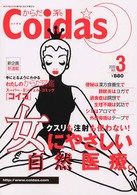内容説明
『司馬遷』の武田泰淳、『魯迅』の竹内好。ふたりの生涯にわたる文学・思想的軌跡を交差的にたどりつつ、日本人にとっての「中国」を浮き彫りにする昭和精神史。
目次
1 戦時下の十年(中国と日本;『中国文学月報』;日中戦争;中国文学研究会と支那学派;大東亜戦争;『司馬遷』;『魯迅』;戦争末期の上海)
2 「戦後」(上海における敗戦;「中国の近代と日本の近代」;国民文学論争;『風媒花』;『歴史』と『時間』)
3 一九六〇年前後(バンドン会議;『森と湖のまつり』;「近代の超克」;安保闘争;アジア主義)
4 「文革」の時代(文化大革命;『秋風秋雨人を愁殺す』;「わが子キリスト」;雑誌『中国』;『富士』)
著者等紹介
渡邊一民[ワタナベカズタミ]
1932年東京生まれ。東京大学文学部佛文学科卒。近現代フランス文学専攻。立教大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
メルセ・ひすい
2
13-72 赤3竹内好⇒今、竜馬デスガ日本文化を魯迅ほど・・・寓話「聖人とバカとドレイ」・・「ドレイ(奴)は、自分が(奴)であるという意識を拒むものだ。彼は自分が(奴)でないと思う時に真の(奴)である」と確認した上で、日本文化の特質をこう開陳する。 日本は近代への転回点において、ヨーロッパに対して決定的な劣勢意識をもった。(それは日本文化の優秀さがそうさせたのだ。)それから猛然としてヨーロッパを追い始めた。●自分がヨーロッパになること、よりよくヨーロッパになることが脱却の道であると観念※2010/04/22