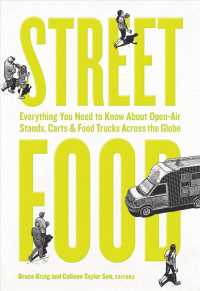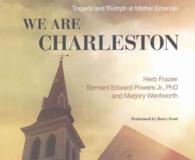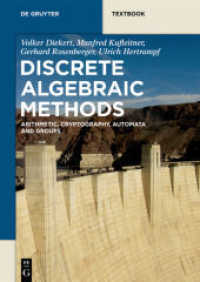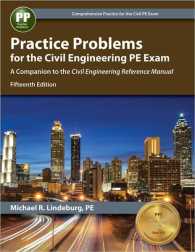内容説明
本書では、読み書きと生存の関係について、とりわけ途上国における「紙とペンの読み書き」の現状、そして今後の展望を考察する。
目次
第1部 読み書きと社会の発展(読み書き研究と国際協力;途上国の読み書き問題に対するリテラシー・アプローチ)
第2部 文書と人間の歴史(文書とはどんな道具なのか?;紙の向こうの誰か;現代世界における文書との付き合い方)
第3部 途上国の読み書き問題―ボリビアの編み物教室で考える(編み物プロジェクトの背景と成り立ち;文書管理エクササイズのメニュー;エクササイズの結果分析)
著者等紹介
中村雄祐[ナカムラユウスケ]
1961年、福岡市生まれ。博士(学術、東京大学大学院総合文化研究科)。現在、東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
samandabadra
0
識字という概念は、文字、数字などぐらいだと思っていたが、地図の読み方や、それらを使った文書のレイアウトなども、その概念に含めるといった「文書管理」アプローチによる議論、読み書きと生存率が正の関係にあり、まさに生きるための読み書きとはどういうものかという議論を極めて説得的に展開。文字の性質、文字によるコミュニケーションの性質に関する議論も非常に勉強になる。後半、編み物教室において、編み物記号を読み解きながら編み物をするという「リテラシー」の実験など、実証もあり、非常に充実した内容になっている一冊2011/01/15