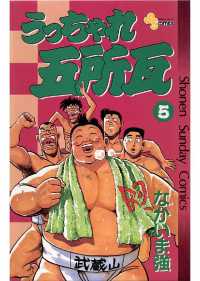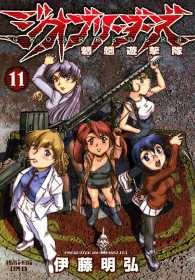内容説明
圧制から解放されたロシアは我々の側に来るのか。1920年、十月革命から2年半後、哲学者ラッセルはイギリス労働党代表団とともに革命のロシアを訪れた。レーニン、トロツキーと会い、都市・農村では人々と対話を交し、多くの文献資料を読んだ。そして、単にこの時点での現地ルポというだけでなく、ソ連社会の本質的な問題を透察した書を著わしたのである。読者は、彼がここで提出し議論した問題のいくつかが、まさにかつてのソ連で具体的な問題となっていたのを見出すであろう。「代議制政府の新形態について興味ある実験」をロシアに期待したラッセルが見たのは、「すでに死滅しかけている」ソヴィエト民主主義であった。革命理論の狂信と不寛容は、同胞の苦悩と悲惨にも盲目な国家のテロルを生む。この書の1948年版の序文に、彼は「それ以後のロシア共産主義の発展は、私がかつて予想したものと似ていなくもない」と書き記した。ロシア共産主義はなぜ失敗したのか。成功の可能性はあったのか。その条件は何か。そしてペレストロイカ以後のロシアを考えるうえでも示唆に富む書。
目次
第1部 ロシアの現状(ボルシェヴィズムの約束するもの;一般的特徴;レーニン、トロツキー、ゴリキー;共産主義とソヴィエト憲法;ロシア工業の失敗;モスクワの日常生活;都市と農村;国際政策)
第2部 ボルシェヴィキの理論(唯物史観;政治を決定するさまざまな力;ボルシェヴィキの民主主義批判;革命と独裁;機構と個人;ロシア共産主義は何故失敗したのか;社会主義の成功の条件)
著者等紹介
ラッセル,バートランド[ラッセル,バートランド][Russell,Bertrand]
1872‐1970。イギリスの哲学者。17世紀以来のイギリスの貴族ラッセル家に生れる。ケンブリッジ大学で数学・哲学を学んだ。1895年ドイツを訪れ、社会民主主義の研究に打込む。1910‐13年にはホワイトヘッドと共に画期的な著作『プリンキピア・マテマティカ』(3巻)を著わし論理学や数学基礎論に貢献した。第一次大戦が勃発するや平和運動に身を投じて母校の講師の職を追われ、1918年には4カ月半投獄される。1920年労働党代表団とともに革命後のロシアを訪問。以後社会評論や哲学の著述に専念し、ヴィトゲンシュタインとの相互影響のもとに論理実証主義の形成によって大きな影響を与えた。1950年哲学者として3度目のノーベル文学賞受賞。また原爆禁止運動の指導者のひとりとして99歳の生涯を閉じるまで活動を続けた
河合秀和[カワイヒデカズ]
1933年京都に生れる。1956年東京大学法学部政治学科を卒業。学習院大学法学部名誉教授。比較政治学担当。中部大学特任教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。