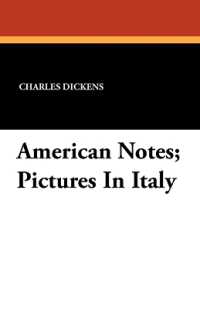内容説明
「祖国」の観念はいつ生まれ、そのために戦いで死ぬことがどうして神聖な行為とみなされたのか―近代国家の成立と宗教性=超越性を二重化したこの問いは、中近世の歴史家であり、二つの世界大戦を経験した著者にとって、切実な問いであった。12、13世紀のヨーロッパ。それまでの中世の王権が古代的な祭政一致的理念をひきずっていたのに対し、この時代に俗権としての国家は、それ自体聖性を獲得するようになった。パウロの手紙以来、教会組織は、頭であるキリストに有機的に結びつく四肢、すなわち「キリストの体」として、象徴的に理解されてきたが、この身体の隠喩が、王を頭とする「神秘体」としての国家という政治理念に転用されるようになったのである。そして全体の体の健康のためには四肢も切断されうるという比喩にしたがって、祖国のための死が、国家という永久不変の神秘体を防衛する聖なる行為とみなされるようになる。本書は『王のふたつの身体』などで知られる天才歴史家カントロヴィッチの代表的6論文を集成した。わが国の王権や国家の象徴儀礼をめぐる研究にも、大いなる刺戟をあたえる書となろう。
目次
中世政治思想における「祖国のために死ぬこと」
国家の神秘―絶対主義の構成概念とその中世後期の起源
「キリスト」と「国庫」
法学の影響下での王権
ダンテの「ふたつの太陽」
芸術家の主権―法の格言とルネサンス期の芸術理論についての覚え書
著者等紹介
カントロヴィッチ,エルンスト[カントロヴィッチ,エルンスト][Kantorowicz,Ernst Hartwig]
1985年、ドイツ領ポーゼン(現在のポーランドのポズナニ)に生まれる。第1次大戦では祖国のために進んで志願兵となり、戦後も左翼を鎮圧する軍で闘うなど、根っからのドイツの愛国主義者であった。ハイデルベルク大学での詩人ゲオルゲとの出会いは大きく、その影響下で1927年、処女作『皇帝フリードリヒ二世』を発表、1932年にはフランクフルト大学の正教授に就いた。しかし翌1933年、ヒットラー政権下でのユダヤ人公職追放に抗議し、翌年辞任、「水晶の夜」事件後にはアメリカ亡命を余儀なくされた。1939年からカリフォルニア大学バークレー校で教鞭をとり、反コミュニズムの嵐に巻き込まれた1950年代、プリンストン大学高等研究所の教授になった。1963年歿
甚野尚志[ジンノタカシ]
1958年福島県に生まれる。1980年東京大学文学部西洋史学科卒業。同大学院を経て、1983年京都大学人文科学研究所助手。東京大学教養学部助教授。ヨーロッパ中世史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Miyoshi Hirotaka
さえきかずひこ
roughfractus02
hatohebi
馬咲