- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 構造主義・ポスト構造主義
内容説明
「私が「私の」本を残すとき、私は、出現しつつ消滅してゆく、けっして生きることを学ばないであろう、教育不能のあの幽霊のようなものになるのです。」最後の対話。
目次
喪を宿す子供としてのデリダ(ジャン・ビルンバウム)
生きることを学ぶ、終に(ジャック・デリダ)
リス=オランジス、二〇〇四年八月八日(鵜飼哲)
著者等紹介
デリダ,ジャック[デリダ,ジャック][Derrida,Jacques]
1930‐2004。アルジェリア生まれ。フランスの思想家。高等師範学校卒業。脱構築、散種、グラマトロジー、差延などの概念を作り出し、ポスト構造主義を代表する哲学者と目される。『フッサール哲学における発生の問題』から出発、ニーチェやハイデガーの哲学を批判的に発展させた。「脱構築」は文学理論や法哲学などにも影響をおよぼしている。1985年から社会科学高等研究院の教授としてセミナーを実践した
鵜飼哲[ウカイサトシ]
1955年東京生まれ。京都大学大学院文学研究科卒業。フランス文学・思想専攻。一橋大学大学院教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
、
21
デリダの遺言的な本。文の意味はわかるけど何を読んだのかよくわからなくなってくる。生と死の二項対立が脱構築され、生に向けて再構築されていくのか、それとも再構築されていないからバラバラの言葉が手からすり抜けていくのか。あれだけやったデリダが脱構築はヨーロッパ的な思想というバックグラウンドがイマイチまだわからなかった やっぱり再読。漠然としたさみしさがありながらも生を賛ずるせつない雰囲気がある。2014/12/16
魚京童!
13
これがどんな形態の本なのかがわからなかった。終に。2024/07/17
シン
13
理解できたとは言い難い。2008/01/17
なかたにか
5
何を書けばいいのか分からない 笑。読んだすきからスルスル抜けていく。この本がデリダの総決算なのか、集大成なのかも分からない。なにかあるのに、手には何もない。蜃気楼みたい。あそこを目指してと、走り出して、走って、この辺りかと止まると、なぜか思った場所じゃない。通り過ぎてる。もう一度目指しても、通り過ぎてる。取り過ぎないように、確認するように読んでいきたいですね。好きな言葉もたくさんありましたし。2014/01/03
🍭
4
135(130西洋哲学>135フランス・オランダ哲学)図書館本。みすず書房2005年4月21日発行。デリダ初読みが図らずも遺稿というのは奇遇。デリダという人は真剣に哲学と西洋(西欧世界)を考えていた人なんだなという認識を得ただけでひとまず充分としたい。生死に纏わる観念を取り扱う哲学だとやはりプラトンから向き合うことになるのか、ということで上半期の小目標に『国家』『饗宴』を読むというのを追加する。プラトンってゴーイングマイウェイ系の理想主義者という先入観があるんだよな。脱構築もやらんとね。がんばろ2025/04/19
-
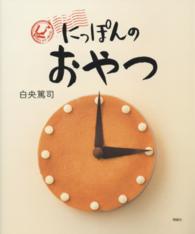
- 和書
- にっぽんのおやつ



![呼び込み君ポポ~ポポポポ〓ポ~チBOOK - あの音が鳴り響く〓 [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/42990/429903709X.jpg)



