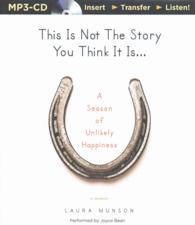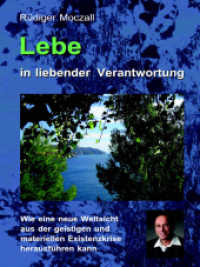出版社内容情報
***
宮中における講学の制は、日本および中国にて古い歴史をもつ。著者は、大正末より昭和初頭にかけて、前後4回、宮中に召されてご進講申し上げた。本書は、その草稿に基づいて文を成したものであり。帝王の学の初めての公開である。
中国では、古来帝王の学として五経、特に聖帝の言を記録した書経をテクストとして用いることが多かった。御講書始の「尚書尭典首節講義」は、その例にならう。
また、「古昔支那儒学の政治に関する理想」「儒学の政治原理」の2篇は、「政は正」という東洋政治の理想――教育感化による人民の安堵を最上とする――を、歴史上の事実、特に歴代の制度との関連において、解き明かす。
これらのご進講において、著者か歴史家としての透徹した予見力をもって、「力」のみに拠る国家の命運を、天皇の御前で説く姿勢には、深い感銘を与えられずにはいないであろう。形式においても、精神においてももはや喪われた真の儒臣の姿が、ここにはある。
内容説明
宮中における講学の制は、日本および中国にて古い歴史をもつ。著者は、大正末より昭和初頭にかけて、前後4回、宮中に召されてご進講申し上げた。本書は、その草稿に基づいて文を成したものであり、帝王の学の初めての公開である。
目次
尚書堯典首節講義
古昔支那に於ける儒学の政治に関する理想(天の思想;徳治主義;儒学の天下思想;民意の尊重)
我国に於ける儒学の変遷(第一期・儒学の渡来より奈良平安朝;鎌倉時代;徳川時代)
儒学の政治原理(政の意義;礼;天子と人民)
付録
著者等紹介
狩野直喜[カノナオキ]
1868年熊本に生れる。1895年東京帝国大学文科大学漢学科卒業。1900‐03年清国留学。1906年京都帝国大学文科大学教授に任ぜられ、支那哲学史を担当。1910年敦煌古書調査のため清国に赴く。1912‐13年欧州留学。1928年京都大学を退官するまでに、支那文学史、清朝経学、論語研究、孟子研究、公羊研究、左伝研究、支那小説史、支那戯曲史、清朝の制度と文学等を講義する。1929年東方文化学院京都研究所長となる。1944年文化勲章受章。1947年死去
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。