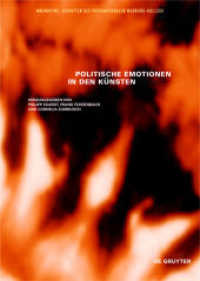出版社内容情報
「漠然と単に一種の教養的読物として、子規の俳論的随筆類に目を遊ばしてみようとする人々の為めによりも、其身、俳句の実作者であると否とに拘らず、昭和現在の俳句及び俳壇の実質と様相、将来の其方向に就いて、関心と熱意とを抱く人々の為めに、先づ、子規の俳句観の骨子をなす材料だけでも提供して、正確に其主旨を理解して貰ひたいと望んで本書を編んだ。説明するまでもなく、昭和の俳句及俳壇の中枢をなしてゐる伝統俳句及び俳句陣は、すべて其源流と基礎とを、明治の子規に発し、子規に負つてゐるものである。子規の良識と事業との存在なくしては、今日の俳句文芸はあり得なかつたのである。されば、今日の俳句文芸の正しい理解はもとより、明日への正しい方向の、検討予測も、子規の俳句観に就いての知識を欠きつゝ樹てることは不可能である」(中村草田男)。
明治期における芭蕉の再検討たる「芭蕉雑談」に、蕪村俳句における積極美と理想美を称揚した「俳人蕪村」、子規の俳句理解の殆どを注入した「俳諧大要」、さらに子規による俳句革新の実況を示す「明治29年の俳句界」など、主要な論考7篇を収録。
------------------------------------------------
正岡子規(まさおか・しき)
1867(慶応3)年松山市に生まれる。松山中学を経て一高、東京帝国大学(中退)。大学在学中、夏目漱石と交友を結ぶ。陸羯南の日本新聞社に入り、俳句・和歌の革新を試みる。1902(明治35)年肺結核にて死去。著書に、『俳諧大要』『歌よみに与ふる書』『病牀六尺』『仰臥漫録』等がある。
中村草田男(なかむら・くさたお)編
1901年、父・修が領事を務めていた中国の廈門(アモイ)に生まれる。本名・清一郎。1904年、母・ミネと二人で帰国し、松山市に住む。1925年東京帝国大学文学部独逸文学科入学、のち国文科に転科。1933年成蹊高等学校(旧制)教授。1949-67年成蹊大学教授、1969年名誉教授。1929年に高浜虚子の門に入り、東大俳句会に入会して「ホトトギス」投句を始める。句集『長子』(1936)、『火の島』(1939)、『萬緑』(1941)を刊行した後、1946年主宰誌「萬緑」創刊。さらに句集『来し方行方』(1947)、『銀河依然』(1953)、『母郷行』(1956)、『美田』(1967)、『時機』(1980)を刊行。この間、メルヘン集『風船の使者』(1977)により芸術選奨文部大臣賞を受賞した。エッセイ集『魚食ふ、飯食ふ』(1979)、評釈『蕪村集』(1943;1980)のほか、評釈・入門書・季語選など10余冊の著編書がある。1983年歿。翌年、芸術院賞恩賜賞受賞。『中村草田男全集』全18巻・別巻1(1984-91、みすず書房)がある。
内容説明
子規が企図した俳句の革新、また写生とは何だったのか?芭蕉と蕪村の比較検討、俳句の形式と本質、明治29年の俳句界など、子規俳論の要をなす7篇を収録。
目次
芭蕉雑談
俳人蕪村
我が俳句
俳諧大要
新俳句と月並俳句
写生といふ事
明治二十九年の俳句界
著者等紹介
正岡子規[マサオカシキ]
1867(慶応3)年松山市に生まれる。松山中学を経て一高、東京帝国大学(中退)。大学在学中夏目漱石と交友を結ぶ。陸羯南の日本新聞社に入り、俳句・和歌の革新を試みる。1902(明治35)年肺結核にて死去
中村草田男[ナカムラクサタオ]
1901年、父・修が領事を務めていた中国の廈門に生まれる。本名・清一郎。1904年、母・ミネと帰国し、松山市に住む。1925年東京帝国大学文学部独逸文学科入学、のち国文科に転科。1933年成蹊高等学校(旧制)教授。1949‐67年成蹊大学教授、1969年名誉教授。1929年に高浜虚子の門に入り、東大俳句会に入会して「ホトトギス」投句を始める。メルヘン集『風船の使者』(1977)により芸術選奨文部大臣賞を受賞。1983年歿。翌年、芸術院賞恩賜賞受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 40歳からの田舎暮らし