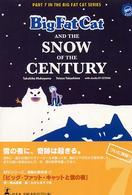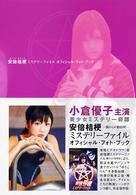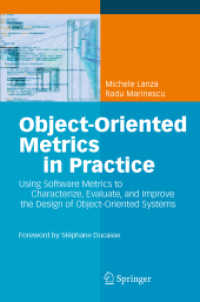出版社内容情報
「いかなる芸術でも、分野独特の〈特殊性〉をもっていて、その〈特殊性〉にまず徹しなければいけない。しかも、それが同時に、作者の内側という内面界において、人間的に豊かな〈普遍性〉をとげることになっていなければいけない。いってみればこの〈特殊性〉と〈普遍性〉とがめでたく重なりえたとき、その文芸の固有性がめでたく実現するのでありましょう」。
「文芸としての俳句のいっさいの問題は、究極的には季題というもののうえに関わってくるということを、ハッキリと記憶しておいていただきたいのです」。
「俳句の場合は、〈季題〉と一つになって存在の根本として把握された〈私〉というものが、つねに主体性として裏打ちされていなければならないのであって、ただ、その主体性としての自己内容が、たんなる個我中に封鎖されることなく、人間として、時代人としての普遍的な豊かさと広がりとを内蔵していなければならないだけのことだと思います。いかなる時代になろうとも、詩文学の根本は、存在一般と奥処において相通った〈私〉――いってみれば〈たましい〉のありなしに関わっているものだと考えます」。
芭蕉以来の俳句の伝統を見据えつつ、実作者としての立場から、「いかに、何を詠むべきか」を懇切丁寧に説き明かした草田男「俳話」集。「現代俳句の諸問題」「現代の俳句」「俳句の『私』と『公』」「俳句の『行』と『考』」「中庸ならぬ中庸の道」「『軽み』について」「芭蕉と平泉そのほか」「岸田劉生のことなど」「啄木の一首などについて」「『おのが哀しきWonne』について」「自覚的自然愛」ほか、全集未収録の22篇。
-----------------------------------------------
中村草田男(なかむら・くさたお)
1901年、父・修が領事を務めていた中国の廈門(アモイ)に生まれる。本名・清一郎。1904年、母・ミネと二人で帰国し、松山市に住む。1925年東京帝国大学文学部独逸文学科入学、のち国文科に転科。1933年成蹊高等学校(旧制)教授。1949-67年成蹊大学教授、1969年名誉教授。1929年に高浜虚子の門に入り、東大俳句会に入会して「ホトトギス」投句を始める。句集『長子』(1936)、『火の島』(1939)、『萬緑』(1941)を刊行した後、1946年主宰誌「萬緑」創刊。さらに句集『来し方行方』(1947)、『銀河依然』(1953)、『母郷行』(1956)、『美田』(1967)、『時機』(1980)を刊行。この間、メルヘン集『風船の使者』(1977)により芸術選奨文部大臣賞を受賞した。エッセイ集『魚食ふ、飯食ふ』(1979)、評釈『蕪村集』(1943;1980)のほか、評釈・入門書・季語選など10余冊の著編書がある。1983年歿。翌年、芸術院賞恩賜賞受賞。『中村草田男全集』全18巻・別巻1(1984-91、みすず書房)がある。
内容説明
芭蕉以来の伝統を見据えつつも、実作者としての立場から、「いかに、何を詠むべきか」を解き明かした草田男「俳話」集。全集未収録の22篇。
目次
現代俳句の諸問題
俳句の「私」と「公」―現代俳句雑感
俳句の「行」と「考」―難解句などの問題にふれて
動いている今
中庸ならぬ中庸の道
現代の俳句
俳句性雑感
現代における俳句の位置
芭蕉と平泉そのほか
自覚的自然愛〔ほか〕
著者等紹介
中村草田男[ナカムラクサタオ]
1901年、父・修が領事を務めていた中国の廈門に生まれる。本名・清一郎。1904年、母・ミネと帰国し、松山市に住む。1925年東京帝国大学文学部独逸文学科人学、のち国文科に転科。1933年成蹊高等学校(旧制)教授。1949‐67年成蹊大学教授、1969年名誉教授。1929年に高浜虚子の門に入り、東大俳句会に入会して「ホトトギス」投句を始める。句集『長子』(1936)、『火の島』(1939)、『万緑』(1941)を刊行した後、1946年主宰誌「万緑」創刊。メルヘン集『風船の使者』(1977)により芸術選奨文部大臣賞を受賞した。1983年歿、翌年、芸術院賞恩賜賞受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。