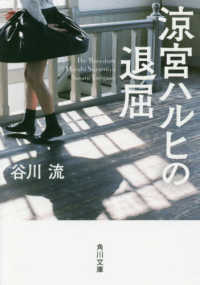出版社内容情報
パリの異端の散歩者として、詩を愛する者たちのあいだで熱烈なファンをもつジャック・レダ。その作品がはじめて日本語で読めるようになった。翻訳はかねてよりレダを敬愛し、自らの指標ともして、デビュー作『郊外へ』でも言及していた作家堀江敏幸。
「かくて私は歩みをつづける、ピチカートで。私は幸せなのだろうか? 悲しいのだろうか? なにかの謎に、意味にむかって歩いているのだろうか? あまり考えすぎないことにしよう。私はもはや、希望のごとく張りつめ、愛のごとく満ち足りた、あの基本和声のふるえにすぎないのだから。」
1970年代、再開発の進むパリ周縁部を原動機つき自転車ソレックスにのった詩人は走り回る。「じつに微妙な仕方で、その崩れかけた空間のなかに、あたらしいなにかを見出そうとする。大手企業の工場が取り壊されたあとの瓦礫の山、小環状線の廃線と切通しの土手に生える雑草、空き地にできた油の浮かぶ水たまり、日曜日のがらんとした住宅街。」(訳者あとがき)ありふれた人生と濃厚な詩魂がスパークする純粋散文集であり、また観光の対極にあるディープなパリ・ガイドでもある。
書評情報:
茅住ヤヒロさん/東京新聞 2001.8.16
Jacques Reda(ジャック・レダ)
1929年リュネヴィルに生まれる。二十代から詩集を出していたが、その後の沈黙を経て、『アーメン』(1968), 『レチタティーヴォ』(1970),『変質』(1975) などの詩集を刊行。本書によって散文への移行を果たす。1987年から1995年まで、NRF誌を編集。本書に続き、『土手の草』『気流の城』『散歩のすすめ』『歩行感覚』『街の自由』など、パリとその周辺を素材にした散文を発表しつづけている。
堀江敏幸(ほりえ・としゆき)
1964年、岐阜県生まれ。現在、明治大学助教授。1999年『おぱらばん』(青土社)で第12回三島由紀夫賞を、2001年『熊の敷石』(講談社)で第124回芥川賞を受賞。著書『郊外へ』(白水社)『子午線を求めて』(思潮社)『書かれる手』(平凡社)『回送電車』(中央公論新社)『いつか王子駅で』(新潮社)。訳書 ギベール『赤い帽子の男』(集英社)リオ『踏みはずし』(白水社)ほか。
内容説明
異端の散歩散レダにかかると街路や郊外がとつぜん息づきはじめる。濃密な詩文集。
目次
逃げ去っていく異端者の足どり
音もなく、ほとんど言葉もなく
灰色のやわらかな厚みのなかで
なにか見出しがたきもの
小さな青い扉
近郊へ
サン=セルジュの祝福
ウォーキング・ベース
停車、ビュッフェ、鉄道網
著者等紹介
レダ,ジャック[レダ,ジャック][R´eda,Jacques]
1929年リュネヴィルに生まれる。二十代から詩集を出していたが、その後の沈黙を経て、Amen(1968)、R´ecitatif(1970)、La Tourne(1975)などの詩集を刊行。本書によって散文への移行を果たす。1987年から1995年まで、La Nouvelle Revue Francaise誌を編集。パリとその周辺を素材にした散文を発表しつづけている
堀江敏幸[ホリエトシユキ]
1964年、岐阜県に生まれる。現在、明治大学助教授。1999年『おぱらばん』(青土社)で第12回三島由紀夫賞を、2001年『熊の敷石』(講談社)で第124回芥川賞を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
兎乃
ぞしま
ぱせり
ぽち
愛玉子
-
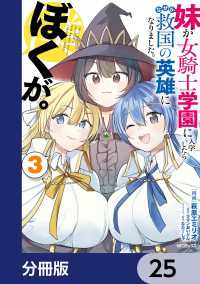
- 電子書籍
- 妹が女騎士学園に入学したらなぜか救国の…