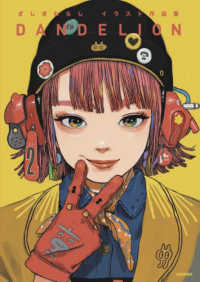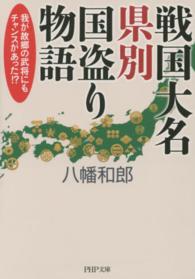出版社内容情報
人間の生命過程と、発達段階。幼児期と社会生活の様態、自我の成長、人間の八つの発達段階など。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
7
ウィーンからアメリカへ亡命する中、無意識を重視するフロイト派の姿勢に距離を取る著者は、自我と社会との関わりを世代的に捉える分析法を固めていく。本書はそのような観点での臨床経験から導き出された幼児期に関する試論である。幼児のてんかん発作、海兵隊員の戦闘危機、幼児性欲の臨床から、フロイトのリビドー論をライフサイクルの変化の指標として用い、自我と社会の関係を段階的に捉える。保護区でのスー族の分析では思春期の無感動を「白人」の「しつけ」への対応とし、幼児期の子育てや玩具との関わりが社会への態度を形成すると捉える。2021/11/13
Re哲学入門者
4
アメリカ・インディアンの2部族とフロイト理論との関連が面白い。それぞれの部族では、大きく幼児期の教育や性格や思想が異なる。しかし、その根底には共通した幼児の発達段階やそれにふさわしい教育が見られる。現代の我々や白人からすると野蛮にみえる教育も常識に反するだけで、間違っている訳では無いと改めて思う。2025/02/16
清水聖
1
精神分析理論を発展させる中でのケースへのアプローチに感心した序盤。理論家≠実践家なんてことは絶対言えない。ベースがしっかりしてるから一挙手一投足が勘でも気まぐれでもないエリクソン先生。そこからインディアンの話を挿んで…文(明)化の中での「子どもの育ちとの関わり」が時々状況に制約を受けながら、それでもなお試行錯誤されていくっていう大きいスケールでのヒトの「育ち」があったり、導引する「何か」が窺えたり。幼児の玩具とその遊びについての論が続いて、全部プレイセラピーの教科書みたいな一画に至る。これが最大の収穫。2023/11/16
godubdub
1
児童心理を考えようと読み始めたが、刺激的な内容だった。守る対象だけの子どもではなく、成長という、ある意味厄介な課題を社会のあり方と共に考えさせてくれる。折りに触れて立ち返りたいと思った。2017/08/15
くめZ
0
子を持つ親として何か役に立てば、と思って手に取ったが難解だわ。幼児の欲求が、「口に入ってきたものを舐める」→「舐めたいものを舐める」→「咥えて(掴んで)保持する」→「保持したり手放したりをコントロールする」、という順で変化する、という点はへーと思った。2014/06/11