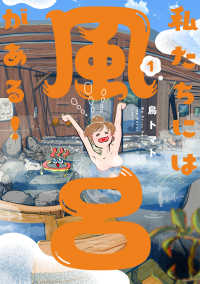出版社内容情報
経験主義と主知主義を批判しつつ世界の意味を開示し、戦後思想に莫大な影響を与えた著者の主著。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
K
10
フッセル、ハイデガー、サルトルと来て、メルポンも読んでみようと思い、とりあえず主著を。以前読んだ竹内の著作に、サルトル批判が『知覚の現象学』にあると知ったので、それがメインでもある(もっともそれは下巻だが)。知覚とは、つまりは世界がわれわれにとって存在するようになることであるが、その探究が『知覚の現象学』である。第一部では、身体論が展開される。「自己の身体こそ、図と地という構造にいつも暗々裡に想定されている第三の項であって、一切の図は、外面的空間と身体空間との二重の地平の上に姿を現すわけである」云々。2023/03/04
グスタフ
9
「現象学はバルザックの作品云々とおなじように、ふだんの辛苦である」と書き、この本の序文が締められる。例えば哲学について「おのれ自身の端緒の常に更新されてゆく経験」「芸術と同じく或る真理の実現」などと語る。フッサールの砂をかむような文章と比べて、メルロはなんと豊かな表現力をもつことか。シビれる文章が満載で、楽しい本。これが、哲学書の正しい在り方かどうかは疑問の残ることだが・・・2013/09/23
の
4
分析哲学に反対し、何よりも第一に存在する知覚の存在から関連付け、身体や行動の原理へと論理が展開する。「自他の癒合する身体」、つまり自分の身体と他者の身体は根底において融合しており、だからこそ人間は他者の知覚を理解することができるのだという。また、そこから他者の統合物である「世界」に対して向き合って生きる「身体的実存」の見解が、現在哲学の「志向性」概念と深く結びついていることも見逃せない。2011/05/13
井蛙
2
幻影肢は生理学的説明でも心理学的説明でも満足させることができない。それはむしろ現象学的地平から理解するべきである。そして現象学の最も重要な知見が世界内存在であるとするならば、身体というものが際立った形で現れてくるのが分かる。身体とは認識の座でも認識の対象でもなくむしろ両者の往還、常に投企する実践的可能性である。メルロ=ポンティは身体のこの両義的な世界に対する関わり方を身体図式と呼んでいるが、これによって彼はデカルト以来の二元論を超克しようとする。2018/01/23
☆☆☆☆☆☆☆
2
やっと読めた。『存在と時間』の問題意識を身体的側面から追いなおすような印象で、心と身体のデカルト的分離の誤りをさらに徹底的に暴いてゆくのはもちろんのこと、身振りや言葉がそのものにおいて意味を持つという議論につながるのが面白い。下巻も期待。2015/09/13
-

- 電子書籍
- 文系のための統計学入門---データサイ…