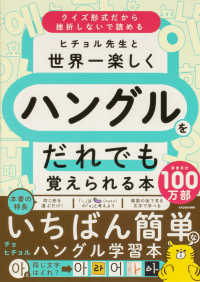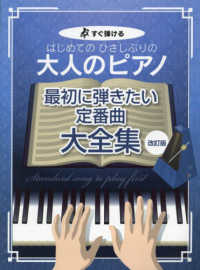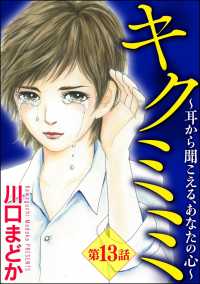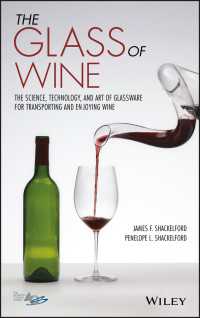出版社内容情報
フッサールの現象学の展開を把握しサルトルへの批判を示す「人間の科学と現象学」ほかを収める。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
eirianda
13
初メルロ=ポンティ。眼と精神を読みたくて借りる。読みながら精神を動かすものは(見えるもの)だけではないよな、と思うのだった。すべての感覚が情動に働くはず。今ほど脳科学が発達した時代においてはいろいろと思考も変わってしまってなかなかのめり込めなかった。哲学だけでなく幼児の対人関係についても書かれていて意外だった。現象学って…何を読んでもよく分からず。阿保なのかな?私が!2021/10/06
みき
11
超越的視点による現象の分析は、実際には幽体離脱的に行われている。超越的視点は、自らの状況をカッコ入れすることではなく、まさしく超越的に少し上から眺めることなのだと考える。私は小説という現象を、超越的視点から分析したいと思って、その方法を探るべくこれを読んでみたけれど、ほんの少しだけそのやり方がわかった。やってみれるかは別だけど。2023/04/07
彩菜
10
私達が何かを見る時、そこには心と身体二つの視点がある。私が手を見る時、心は手を「見て」いるけれど身体である手は「見られて」いる。私が世界を見る時、心は世界を見ているけれど身体は見られている世界の中にある。この二つの視点の交差で私達は自分や物がそこに「存在する」と感じている。画家はこの秘密を知っていて光や色彩、奥行きでこの「存在」とは何かという事を私達に描き出してくれる。これが絵画の根源だと著者は言う。このようになのかは分からないけれど絵画が目の前の「存在」を見つめてきたのは間違いないんだろうな。2018/08/11
wadaya
8
私が今から述べることは、もはや「眼と精神」の内容から逸脱しているので、メルロ・ポンティを読む参考にはしないでほしい。あくまで持論。戯言として読んでほしい。私は中学の卒業文集に「眼」というタイトルの散文を書いたのを覚えている。(引越しの際にアルバムごと紛失した汗)今思えば、拙筆ではあるが、私はきっと眼を通したものが、心のスクリーンに映し出されると言いたかったのだろう。子供の頃から「眼」と「心」の関係性に興味があった。メルロはサルトルと同じく実存主義者であるが、一線を引いていた。元はデカルトから始まっている→2024/03/27
zumi
6
難解でまだ理解不十分。絵画に「奥行き」が存在するのは何故か? それは「見る」という行為が目の届く範囲しか認識できないからであり、対象を離れて所有するーーその距離が「奥行き」として現れるからに他ならないからだ。我々は身体(眼)の動きによって、視覚を視覚たらしめる。同時に身体(眼)の動きは、心の動き=思考を発生させる。故に、画家は「見ること」によって視覚の中に対象を存在させ、像を画布に描く。それは実在するものでなはない。そこに現前するのは実在するものと、物を見つめる視線の反射によるものーー類似にすぎない2014/01/15