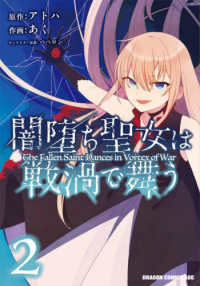出版社内容情報
中世から18世紀までの子供をめぐる家族生活に注目し、現代の <子供> 概念が誕生する背景を探る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
シルク
10
再読。むずかしい。けどおもしろい。前読んだのは4年前でしたが、「大分理解出来るようになってきたかなぁ~」なんつってつぶやきながら、肝心なところを誤読していた😖 何かっつーと、前は「アリエスは墓碑の研究をしていて、ある時期より前は、夭折したこどもの墓で、亡くなったその子の姿を墓碑に刻むことがないと気が付いた。ある時期以降、幼くして死んだ子の姿を刻んだ墓碑が登場する。アリエスは、死んだ子の姿を刻んだ墓碑の登場の背景に、幼い者に対する、今日的な感覚の芽生えを見て取った」…と読んだけど、ちょっと、ずれていたわ。2025/05/07
koke
10
この本を読みこなすには十分な知識や教養がなくとりあえずの通読となってしまいました。が、名著と言われるだけの内容だとは感じられました。膨大な資料の引用とそこから導き出される西洋の精神史。私たちの考え方がどこからやってきたのかを知るにあたっての歴史学という学問の価値がよくわかりました。これだけの仕事をしたアリエスが大学に属さず、日曜歴史家であったということに驚嘆してしまいます。2023/08/31
シルク
9
「中世ヨーロッパにこどもはいなかった」であまりに有名な本。この本が自分にとって、「読書力、ちったあ伸びたかしら?」「ちょっとは頭ましになった?」…を測る本であり続けてはや8年。学生の時分食費おさえてうどん(1玉12円)ばっか食べて買ったなあ…。しみじみ。ーー以来8年。第1部は既に持っている知識を補助になんとか理解するも、第2部〜がいつもさっぱり分からず、頭がぱぴぷぺぽだった!今回ようやく全体が分かったぞ…意識遠くならずに読みきったぜ!うひ♪そして…おっもしろーい!!やっぱりこういう古典は生を読むに限るな。2014/11/10
梟をめぐる読書
7
「アリエスの主張はすでに論駁されている」という理解ばかりが先行して、興味深いテーマにも関わらずなかなか手が出せなかった一冊。確かに「近代まで西欧には私たちの考える(保護され、愛でられる対象としての)<子供>はいなかった」という主張をそのまま鵜呑みにすることは難しいが、しかしフーコーいうところの“エピステーメー”の問題として読めば、「<子供>観の普遍性」という常識に初めて疑義を呈したこの本の価値も多少は見えてくる。そのフーコーもまた論駁されているのだというから、哲学は面倒くさいのだけど。2012/08/24
富士さん
5
初めて読んだときは「あぁ、子供は構築された概念だんだ」くらいのぼんやりとした読後感でしたが、改めて精読してみて本書の偉大さに気づきました。議論が周辺から徐々にテーマに収斂されていく形で行われるので、著者の意図がすんなり入ってきませんが、学校によって子供と家族は作られ、学校は近代資本主義社会によって作らた。つまりは子供と家族は近代社会によって作られた、という壮大なテーマを跡付けたのが本書なのだと理解しました。当然、子供服はあった、みたいな瑣末な批判は批判者の浅慮しか表さないのは言うまでもないでしょう。2016/02/25
-
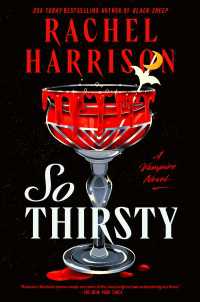
- 洋書電子書籍
- So Thirsty
-
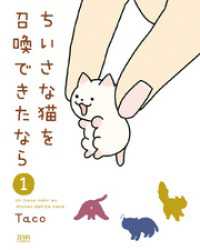
- 電子書籍
- ちいさな猫を召喚できたなら 1巻 ゼノ…