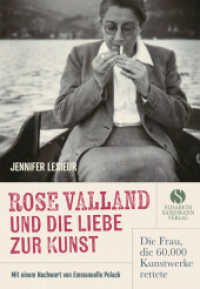出版社内容情報
国立文化財機構 文化財防災センター監修による、文化財防災を総合的に学ぶための一冊。日本は地震、台風、豪雨などの災害が多発する国である。災害が起こればその地にある文化財も被災する。混乱する状況の中で、いかに文化財をまもってきたのか、そしてこれからどのようにまもっていけばいいのかを本書では総合的に概観する。
本書では文化財防災の体制づくりの歩みから、各組織・団体の取組み、文化財防災センターを中心としたネットワークの構築、被災した文化財の応急処置の方法までを丁寧に解説。加えて、被災した文化財を活用するという視点を具体的な事例とともに紹介する。
自然災害による被害を完全に避けることは難しいかもしれない。しかし、適切な備えと知識があれば、大きく減らすことはできる。文化財は、ときに地域へ希望をもたらす存在にもなる。本書をもとに、多くの文化財がまもられ、未来へと受け継ぐ一助となることを期待する。
【目次】
はじめに
1 章 わが国の文化財防災の展開
1.1 文化財防災の考え方
1.1.1 文化財防災の基本
1.1.2 文化財防災スパイラルの四つのプロセス
1.1.3 社会的インフラとしての文化財
1.2 わが国の文化財防災のあゆみ
1.2.1 廃仏毀釈と近代文化財保護制度の黎明
1.2.2 濃尾地震と本格的な災害対応,防災活動のはじまり
1.2.3 関東大震災と被災文化財の記録
1.2.4 法隆寺金堂火災と文化財保護法の制定
1.2.5 阪神・淡路大震災と未指定文化財などへの対応や全国ネットワークによる活動
1.2.6 東日本大震災と文化財防災センターの設立
1.3 阪神・淡路大震災の文化財レスキュー
1.3.1 阪神・淡路大震災被災文化財等救援委員会の設立
1.3.2 救援委員会の活動事例
1.3.3 阪神・淡路大震災の文化財レスキューのレガシー
1.4 東日本大震災時の文化財レスキュー事業
1.4.1 文化財レスキュー事業による救援活動開始まで
1.4.2 石巻文化センターでの救援活動
1.4.3 文化財レスキュー事業終了後の展開
1.5 文化財保存修復学会における災害対応の取組み
1.5.1 文化財防災の普及を目指した災害対策調査部会の活動
1.5.2 被災文化財への支援活動
1.6 全国美術館会議における災害対応の取組み
1.6.1 1993 年のワーキンググループの発足と地震対策の研修会
1.6.2 阪神・淡路大震災での救援・支援活動と調査研究,および情報共有
1.6.3 「大災害時における対策等に関する要綱」と高知豪雨
1.6.4 東日本大震災での対応と報告書と記録集の刊行
1.6.5 文化財レスキュー事業から見えてきた課題とその後の展開
1.6.6 災害対策委員会の発足とその後の取組み
1.7 自然史資料の保存管理と災害対応
1.7.1 自然史資料,自然史標本とは
1.7.2 誰がまもるのか,そのために何が必要なのか
1.7.3 自然史資料保存の未来のために
1.8 無形文化遺産情報ネットワークの取組み
1.8.1 無形文化遺産情報ネットワーク起ち上げの背景
1.8.2 無形文化遺産情報ネットワークの起ち上げ
1.8.3 データベースとしての無形文化遺産情報ネットワーク
1.9 地域歴史資料を取り巻くネットワーク――地域と大学・専門家をつなぐ取組み
1.9.1 地域を主体とした資料保存・継承の展開
1.9.2 人間文化研究機構によるネットワーク構築の取組み
1.9.3 持続的なネットワーク構築に向けた取組み
1.10 日本建築学会の取組み
1.10.1 文化財建造物の防災のはじまり
1.10.2 阪神