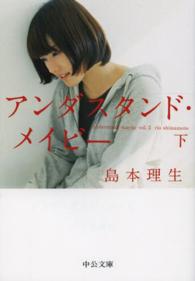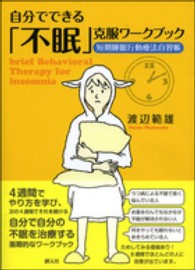出版社内容情報
本書は、建築分野において構造形態創生と呼ばれる連続体のトポロジー最適化について、粒子法を用いた構造解析理論とExcel VBAを用いた構造解析ソフトウェアの作成方法を解説しています。
本書の特徴のひとつが、最適化の対象となる構造物の解析に粒子法を用いていることです。粒子法を用いることで、構造が大変形する場合でも解の精度を保つことができる特徴を活かし、微小変形のみならず大変形問題(幾何学的非線形問題)についても扱っています。こうした粒子法の中から、MPS法とその発展形であるHMPS法の2種類を採用しており、両手法についての理論の解説から構造解析、構造形態創生、コンプライアントメカニズムの形態創生に至るまで取り上げています。これらの解析結果については、両手法の比較だけではなく、有限要素法での解析結果についても比較しながら、精度の検証まで行っています。
解説したソフトウェアについてはサポートページで提供もしていますので、ダウンロードすることで本書の解析例を実践することができます。
【目次】
第1章 粒子法による構造形態創生
1.1 はじめに
1.2 粒子法による構造解析に関する既往の研究
1.3 粒子法による構造形態創生に関する著者らの研究
1.4 まとめ
第2章 MPS法による構造解析
2.1 はじめに
2.2 粒子法の基礎式
2.2.1 微小変形理論の基礎式
2.2.2 弾性論にもとづく粒子法の基礎式
2.3 MPS法の構造解析理論
2.3.1 MPS法の基礎式
2.3.2 MPS法の離散化
2.3.3 第2ピオラ・キルヒホッフ応力テンソルの求め方
2.3.4 動的緩和法による静的解の求め方
2.4 MPS法による構造解析プログラム
2.4.1 データ入力シートの作成
2.4.2 データ入力
2.4.3 構造解析プログラムの作成
2.5 MPS法による構造解析結果の考察
2.6 まとめ
第3章 HMPS法による構造解析
3.1 はじめに
3.2 HMPS法の構造解析理論
3.2.1 HMPS法の離散化
3.2.2 静的解の求め方
3.2.3 局所的振動を抑制する方法
3.3 HMPS法による構造解析プログラム
3.3.1 データ入力シートの作成
3.3.2 データ入力
3.3.3 構造解析プログラムの作成
3.4 HMPS法による構造解析結果の考察
3.4.1 微小変形における比較
3.4.2 大変形における比較
3.4.3 局所的振動の抑制効果
3.5 まとめ
第4章 MPS法による構造形態創生
4.1 はじめに
4.2 構造形態創生問題の解法
4.2.1 構造形態創生問題の定式化
4.2.2 IESO法の感度指標
4.2.3 IESO法の要素除去アルゴリズム
4.2.4 IESO法の要素付加アルゴリズム
4.2.5 IESO法の仕上アルゴリズム
4.3 MPS法の構造形態創生問題への適用
4.3.1 MPS法の要素ひずみエネルギー
4.3.2 要素除去に対する粒子除去
4.4 MPS法による構造形態創生プログラム
4.4.1 データ入力シートの作成
4.4.2 データ入力
4.4.3 構造形態創生プログラムの作成
4.4.4 グラフィックス表示プログラムの変更
4.5 MPS法による構造形態創生結果の考察
4.6 まとめ
第5章 HMPS法による構造形態創生
5.1 はじめに
5.2 HMPS法の構
内容説明
本書は、建築分野において構造形態創生と呼ばれる連続体のトポロジー最適化について、粒子法を用いた構造解析理論とExcel VBAを用いた構造解析ソフトウェアの作成方法を解説しています。
目次
第1章 粒子法による構造形態創生
第2章 MPS法による構造解析
第3章 HMPS法による構造解析
第4章 MPS法による構造形態創生
第5章 HMPS法による構造形態創生
第6章 MPS法による機構形態創生
第7章 HMPS法による機構形態創生
第8章 作成したソフトの使い方
著者等紹介
藤井大地[フジイダイジ]
近畿大学工学部建築学科教授。1992年6月広島大学大学院工学研究科博士(工学)取得
眞鍋匡利[マナベマサトシ]
株式会社増岡組。2009年3月近畿大学大学院システム工学研究科修士(工学)取得(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。