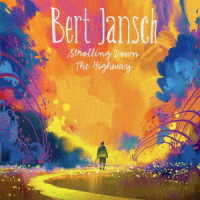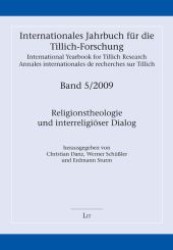内容説明
量子論の発展する19世紀から20世紀初頭の物理学者たちの興味深いエピソードなど、科学史的話題をもり込みながら、初学者向けにわかりやすく解説する「電磁気学」の入門書。古典的現象である電磁気学に量子論的な視点をとり入れ、電磁気学の発展を現代的視点でとらえ直し、発見や理論的成熟の歴史をたどりながら電磁気現象についても言及することで、現代物理へどうつながるかも提示するユニークな構成。パリティ誌の人気連載講座「電磁気現象にみる古典と量子の交叉点」の単行本化。
目次
ファラデーの着想:力線の登場
ファラデーからマクスウェルへの道
マクスウェルの貢献
場の実在性と2人の畸人
ベクトルポテンシャルは物理的に実在するか?
電子の登場:「場」と「粒子」の共存
世紀末の物理:量子論の夜明け
アインシュタインの登場
黒体輻射から遷移確率へ
ファインマンの経路和と量子の束縛
量子の幾何学としての電磁相互作用:ゲージ原理への道
電磁場のパラダイムの変遷:エーテルの行方
輻射熱と電磁場の合流:熱から黒体輻射へ
著者等紹介
筒井泉[ツツイイズミ]
高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所准教授。理学博士。ハンブルク大学博士研究員、ダブリン高等研究所研究員、東京大学原子核研究所助手を経て、現職。おもな研究分野は場の量子論、量子基礎論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
2
ふむ2024/12/08
ゆうちゃん
1
熱と電磁気と量子力学の関係性を歴史と数式の異なる視点からパラレルに学べる。数式は特に量子力学のものは理解困難だったが著者の文才でカバーしてもらえた。目に見えないもの測定できないものに浪漫を感じ、これからまだまだ人類はどこへ進もうというのか。2023/10/12
hhhhhhaaaaaa2
1
電磁気の量子力学の簡単な発展史である。電磁気はファラデーから、量子力学は黒体輻射の問題から始まり、非可換ゲージ理論までの内容が150ページ程度にまとめられている。19世紀末以降の物理学の歴史を大雑把に把握するにはちょうどよい本であるが、込み入った詳細は参考文献を読む必要がある。多くの歴史書では電磁気の発展は相対性理論との関わりの中で論じられることが多いが、本書の特徴は電磁気が量子力学とどのように関わりをもち、そして現代まで発展してきたかが書かれている点である。
Steppenwolf
1
E2019年に廃刊したパリティに一年間連載された記事を単行本化されたのが本書である。恥ずかしながら雑誌を購読していたのに読まず単行本になってから読むとは,何たる無駄。内容は電磁場概念と量子論,特にアインシュタイの仕事と絡めて説明されている。そして私の電磁場に関する認識が如何に浅いものであったかということを恥じながら読了した。本書は本来電磁気学と量子論を勉強しながらあるいは終えてから学生が読めば理解が深まるだろう。37ページ脚注に年代のミスがある。2020/02/04
N
0
電磁気学の発展史が量子力学との関連を意識して書かれている読み物。ベクトルポテンシャルは古典では補助的概念に過ぎない一方量子ではむしろ物理的実在だと見なされていることは有名である。これに反して量子でもベクトルポテンシャルは物理的実在ではないと考えられるという近年の説の話が面白かった。また、エーテルは今でも完全に否定された概念ではなく、局所実在論の破綻をエーテルの存在を導入することで説明できるのではないか、というBellが提唱したアイデアについての話も興味深かった。2022/02/09
-

- 電子書籍
- 週刊ファミ通 【2022年3月3日号】…
-

- DVD
- 崖っぷちの熟女たち