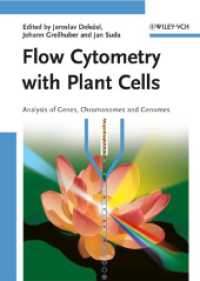内容説明
群論は、自然界に内在する規則性を、より統一的に把握するためにたいへん有効であり、物理学を体系的に学ぶために不可欠のものである。本書は、群の中でも物理によく出てくる「リー群」を中心に、概念をつかんで使えるようになることを目標としている。数学的基礎概念から具体的応用まで、物理的内容に例を取りながら解説した本書は、量子力学・ゲージ理論を理解し、発展的に使いこなすために、おおいに役立つ。本書により物理学の展望が開けることであろう。「パリティ物理学コース 物理数学特論 群と物理」待望の改訂。
目次
1 物理法則と対称性
2 群の基本概念
3 リー群とリー代数
4 リー代数の表現と分類
5 ユニタリ群とその表現
6 直交群とその表現
7 その他のコンパクト群の表現
8 ローレンツ群
付録 表現の直積の既約表現への分解
著者等紹介
佐藤光[サトウヒカル]
1966年東京大学理学部物理学科卒業。1971年同大学大学院理学系研究科博士課程修了。理学博士。同年同大学理学部助手。1973年メリーランド大学物理天文学部ポストドクトラルフェロー。1975年ミネソタ大学物理天文学部ポストドクトラルフェロー。1981年兵庫教育大学助教授。1988年同大学教授。2001年同大学副学長。2008年同大学名誉教授。専門は理論物理学(素粒子論)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やす
13
全然歯が立たなかった。表題の通りの本。1章は見たことないぐらい結晶群を網羅的にうまく説明している。2章の群の定義はこれだけでわかる人は天才レベル。でも物理の方程式に対する群の作用の説明はすばらしい。ただし量子力学の入門済の人対象。3章のリー群とリー代数も表題自体はよいとして多様体としてのリー群とかコンパクトとか連続群論をねじ込んでくる。すごいなあ。ここまでなんとかついていったのだが次の章で遭難する。ここまで82P全体の1/3。4章はリー代数の表現と分類。アインシュタイン記法でつまずく。計算ができない。2024/02/21
BIN
6
挫折。物理(量子力学)で出てくるリー群について詳しく知りたくて本書を手にとった。最初は物理での対称性について触れてわかりやすいかもと思っていたら、群論に入ると数学的で一般化されていて、全然わからない(ところどころ量子力学ぽいとは思ったが)。結構計算を端折ってる気もする。たぶん物理的にも数学的にも中途半端なのかもしれない。物理も群論もある程度知っていて、両方の関連付けを知るために読む分にはよいのかもしれない。もう少し他書で勉強して再チャレンジかな。2022/03/23
-
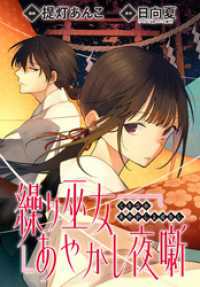
- 電子書籍
- 繰り巫女あやかし夜噺 【連載版】: 6…
-
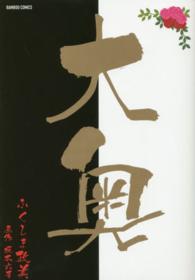
- 和書
- 大奥 バンブーコミックス