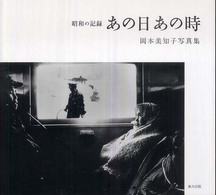内容説明
本書では、地球こそが宇宙の中心であるという考えが間違いだとわかった時代から、宇宙探査の歴史をひもとき、ブラックホール、ダークマター、太陽系外惑星の発見など、最近の研究までをたどります。前作『太陽系探査の歴史―宇宙に近づく22のアクティビティ』とあわせて、人類の宇宙にかんする知識がどのように積み重ねられてきたかがわかるでしょう。さらに、科学者たちのコラム、主要な発見のタイムライン、最新の情報を追うためのウェブサイト、21のアクティビティ「ためしてみよう!」といった魅力的なコーナーが、ストーリーの中核をなす歴史に彩りを添えています。
目次
1 先史時代から1600年代まで:星見る人から科学者へ
2 1600年代:望遠鏡と重力が教えてくれたもの
3 1700年代~1915年:恒星を理解する
4 1900~1940年:時空のトリック、島宇宙、ビッグバン
5 1930年代~1970年代:見えない天体クエーサー、パルサー、ブラックホールの発見
6 1980年代~2010年代:泡状銀河、太陽系外惑星、ダークエネルギー
著者等紹介
カーソン,メアリー・ケイ[カーソン,メアリーケイ] [Carson,Mary Kay]
子ども向けのノンフィクション作品を30冊以上執筆。そのうち『太陽系探査の歴史―宇宙に近づく22のアクティビティ』と“The Wright Brothers for Kids(ライト兄弟)”は、アメリカ航空宇宙工学協会の児童文学賞を受賞した
谷口義明[タニグチヨシアキ]
愛媛大学宇宙進化研究センターセンター長・教授。理学博士。2007年より現職。銀河、巨大ブラックホール、ダークマター、宇宙の大規模構造などの研究を行っている
鈴木将[スズキショウ]
東京都立大学理学部物理学科、人文学部心理学専攻卒業。元東京都立高等学校教諭。科学読物研究会会員。都立永福高校では都立高校で初めてフーコーの振り子(高さ7メートル)をつくり、生徒と実験・研究をする
鈴木理[スズキサトシ]
東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。専門は地震・火山関連の研究。コンピュータ会社に入社、セキュリティ関連製品担当。退社後、コンピュータ関連の翻訳に携わっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。