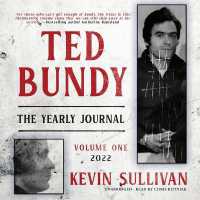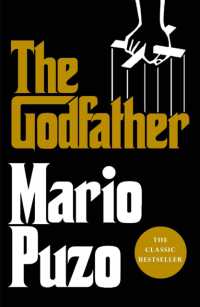内容説明
本書ではアジアの天文学史という文脈の中に、日本天文学の歴史を位置づけた。第1部では、古代オリエントとギリシア、インド、中国、朝鮮および東南アジアの天文学史を概観し、第2部の日本天文学史へと展開する
目次
第1部(古代オリエント・ギリシアの天文学;インドの天文学;中国の天文学;韓国、東南アジアの天文学)
第2部(古代・中世の日本天文学;南蛮天文学と鎖国;科学的天文学の始まり:渋川春海と将軍吉宗;西洋天文学の導入と江戸天文学の発展)
エピローグ 天文学の明治近代化
著者等紹介
中村士[ナカムラツコウ]
理学博士。東京大学理学部天文学科卒業、同大学大学院理学系研究科修了。東京天文台(現在の国立天文台)に入所、NASAのスペーステレスコープ科学研究所研究員(1984~85年)などを経て、2007年に国立天文台を定年退官。2008~14年、帝京平成大学教授。専門は太陽系小天体の研究と江戸時代の天文学史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みかん。
3
古代ギリシャ·インド系の天体の計算方法や翻訳された書籍等が日本に伝わっていた可能性もあるように感じました(宿曜占星術や紫微斗数等)。国産ロケットの開発者が西洋占星術の本を著して日本の今の占いブームもある訳ですからね。2025/11/08
takao
3
ふむ2024/08/13
月をみるもの
2
「はやぶさ」に搭載されて、イトカワの画像を撮ったカメラ AMICA の開発をしていた著者による、東洋天文学史。冒頭の気候変動/四大文明/天文学の始まりの関わりについての仮説が興味ふかい。江戸期の天文学については天地明察よりも http://bookmeter.com/b/4404034148 がおすすめ。2014/12/24
霹靂火 雷公
1
前作『西洋天文学史』でヨーロッパ、三村太郎『天文学の誕生』(岩波書店・2010)でイスラム&インドの天文学を眺めたあとに読了。この3冊で古代から続く天文学の大まかな流れは掴める。2015/06/07
(00)
0
インド以東の暦学(天文学)の概説。かつての天文学は暦学・占星術だった。これまでどうしても暦学に興味が持てなかったが、暦から天体現象を予言する営みが、そのまま当時の宇宙観に繋がると知り、へーっと感心しながら読み進められた。後半は江戸時代に活躍した天文学者のお話。日本にも熱心な学者たちとそれを支える偉い人々がいたことが新鮮だった。 全体的に西洋文化の伝来が度々ブレイクスルーを起こしており、西洋強し...!!という印象。また、著者の「と思う」が多いので、どれだけ研究者の合意が得られているのか気になるところも。2017/12/29