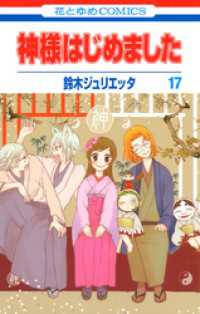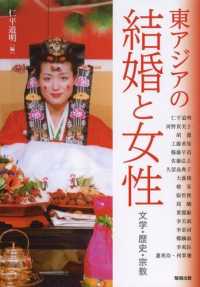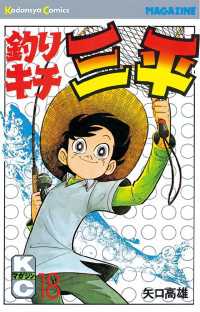出版社内容情報
ウイルスはどこから来て、何を引き起こし、どこへ行くのか? ウイルスというものを丸ごととらえて理解する新しい読み物。
内容説明
人類のウイルス観の変遷、感染のしくみ、さまざまな感染症の起源と現状、治療技術の進歩、ウイルスの地球生命圏における役割、そして私たちとウイルスとのこれからの付き合い方に関する提言まで、ウイルスの全体像を描き出す。この小さな賢い寄生体がどこから来て、本当は何がしたくて、どこへ向かうのか。それを考えることのできる一冊。
目次
1 ウイルスとは?
2 世界中ウイルスだらけ
3 殺すか殺されるか
4 新興ウイルス感染症
5 流行と大流行
6 持続感染ウイルス
7 腫瘍ウイルス
8 形勢逆転
9 ウイルスの過去、現在、未来
著者等紹介
クローフォード,ドロシー・H.[クローフォード,ドロシーH.] [Crawford,Dorothy H.]
英国の医学者。ウイルスとヒトの腫瘍に関する研究に従事。2005年に医学と高等教育への貢献で大英帝国勲章を受章。2007年よりエディンバラ大学のPUM(一般市民の医学の理解)部門の教頭を務める
永田恭介[ナガタキョウスケ]
1953年生まれ。筑波大学学長。薬学博士。アルバート・アインシュタイン医科大学博士研究員、スローンケタリング記念がんセンター研究員、国立遺伝学研究所助手、東京工業大学准教授、筑波大学基礎医学系教授などを経て2013年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
88
今が読み時!と思って。冒頭に”ウイルスについて一般読者に紹介する入門書”とあるが、なかなかどうして医系大学生に対する入門書とか副読本のような感じもする。確かに難しいことは余り書いてないとは思うが、専門用語が多くたびたび巻末用語集のお世話になりながら何とか読んだ。もうコロナが来ても大丈夫…なわけはないけど、取りあえずウイルス側の事情も少々理解できた。ケーススタディとしてHIV(エイズに進行)や2003年のSARSが取り上げられていたが、今度のコロナのパンデミックも将来、教科書に載ることになるに違いない。2020/03/18
翔亀
31
【コロナ14】オックスフォード大学出版社の最近の入門書シリーズ「Very Short Intrduction」の一冊。すでに600冊以上刊行されている新書版。フランスのク・セジュみたいなものか。翻訳は岩波他さまざまな出版社から出ていて100冊にのぼる。丸善出版からはもっぱら理工系のみ。と、周辺情報に字数を費やしたのは、理系の特にライフサイエンスを一般向けに紹介する優れた著作は、英国のライターに多い印象があって、本書も大いに期待したからだ。しかし、病原体としてのウイルスだけでなく、↓2020/05/27
kasim
29
人間中心主義に過ぎないと分かっていても、こんな生き物かどうかも分からないものに世界が壊されていくのは悔しい。RNAタイプ(インフルエンザやコロナも)に至ってはDNAさえ持ってない。遺伝情報プラスたんぱく質の殻。何も考えていない。細胞膜がないから、宿主(患者)にダメージを与えずウイルスだけに効く薬が作れない。すべてのウイルスに対し抗ウイルス薬は2011年現在40種ほどで、その多くがHIVとインフルが対象。『はたらく細胞』が精一杯の文系頭では専門的な部分は難しかった。2020/03/23
まえぞう
13
読書メーターに登録する前に一度読んだものですが、コロナのこともあり読み返しました。SARSは上手く対処したとのイメージで書かれていますが、今回のケースはどう評価されるのでしょうか。自分では代謝機能を持たないウイルスが、なぜおにっ子のようにこの世界に存在するのか、その辺の議論も聞いてみたいです。2020/04/11
シロクマとーちゃん
6
人や動物に感染し、病気にするウイルスは全ウイルスのうちのごく一部に過ぎない。世の中には微生物に感染するウイルスがごまんといるし、海洋中のウイルスは毎日海洋微生物(プランクトンなど)の20-40%を死滅させているらしい。つまり、海産物の栄養源になるはずのバイオマスを分解し、二酸化炭素に変換していることになる。地球の生態系の一部として無視できない。また、遺伝子の運び屋として、生物の進化にも影響を与えてるのは間違いないから、地球上の生物圏全体を支配していると言っても過言ではないかも。2020/03/08