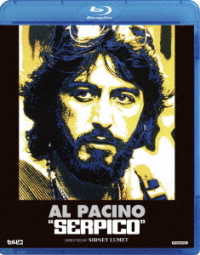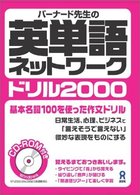内容説明
周期表にまつわる歴史が元素と人間・社会とのかかわりを教え、同位体が暮らしにどれほど役立っているかを示し、金・酸素・鉄・ケイ素・パラジウム・貴ガス・レアメタルなどを例に、歴史や暮らしと元素の深い関係を伝えます。
目次
1 アリストテレスの4元素
2 化学革命と命の元素―酸素
3 欲望と呪いの元素―金
4 7行に並ぶ自然界―周期表
5 よみがえる錬金術―元素変換
6 大活躍する兄弟原子―同位体
7 暮らしを支える元素たち
著者等紹介
ボール,フィリップ[ボール,フィリップ] [Ball,Philip]
1962年英国生まれ。オックスフォード大学で学士号(化学)、ブリストル大学で博士号(物理学)を取得。『ネイチャー』誌の常設コラム“Chemistry World”主筆
渡辺正[ワタナベタダシ]
1948年鳥取県生まれ。東京理科大学教授(東京大学名誉教授)。工博。専攻は電気化学、環境科学、化学教育など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
16
周期表の世界では元素は一貫した秩序の下に並び、そこでは全ての元素は基本的に平等だ。しかし人間にとってはそうではない。人間の文明や文化に寄与してきた重要性によって、例えば金や酸素といった元素は他の元素を遥かにしのぐ存在感がある。そうしたソフトな「元素感覚」を中心に、近代元素に限らず、アリストテレスの四元素やフロジストン説までも視野に入れた、元素の文明史を描いている。例えば金に取り憑かれた人間の悲喜劇や神話と、実際の金の化学的特性や発見を見事に絡めた記述が上手い。人間との関わりという軸が効果的に発揮されている2016/06/12
へんかんへん
1
SF描きたいから科学と医学を知ろうと2015/06/16
アドソ
1
「ピアノの先生は全部の鍵盤を弾かせたりはしない」の言葉通り、すべての元素を均等に紹介しているわけではない。人類の、元素そのものに対するとらえ方、向きあい方を中心に書かれている。周期表の発見史、原爆と放射性元素、レアアース、と定番の話題を押さえつつ、カタログ化に堕することのない「文化史としての化学」の本。2013/12/28
ほんだや
0
うううう…これって結構簡単に書いてるんですよね?入門書的なやつですよね?…真ん中すぎくらいか理解出来なくなってきた…。ダメな脳ミソだのう…2014/07/06
-

- 電子書籍
- 新・君の手がささやいている(11)
-
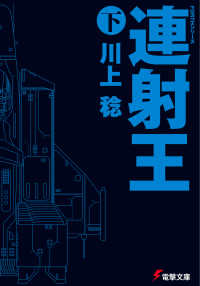
- 和書
- 連射王 〈下〉 電撃文庫