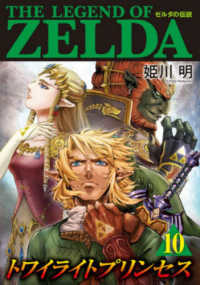出版社内容情報
看護師の必修科目「看護過程」の復習から、わかりやすくまとめられた「看護診断」の理解と実務までを解説。
電子カルテの普及とともに高まる看護診断の需要。特にNANDA-Iは医療機関の多くで採用されています。現在は約1800の病院で電子カルテが導入され、現在もその数は増えています。
しかし、看護教育の現場では、充分に看護診断の授業が行われていないのが現状です。また他では使用されない用語も多く、理解するのに苦労している看護師・看護学生は多くいます。
そこで本書は、看護師の必修科目「看護過程」から、スムーズに「看護診断」が理解できるように執筆されました。1章で「看護過程」を復習し、2章で「看護診断」を理解することができます。そして、3章では、「看護診断」が実際にどのように使われているのかを学び、実務レベルまで高めていくことができます。著者は、学校の授業や病院の看護師向けセミナーで丁寧に分かりやすく教えてくれると高い評価を得ています。
すでに看護診断を使っている看護師から、これから使う看護学生まで、役に立つ一冊です。
第1章 はじめに
第2章 看護過程の確認
看護過程の概要
アセスメントから診断への思考プロセス
第3章 看護診断の理解
看護過程の中での看護診断の位置づけ
看護診断とは何か
NANDA-I看護診断の種類
NANDA-I看護診断の表現方法
看護診断を用いることの意義
看護問題として問題を明確にするプロセスと看護診断として問題を明確にするプロセスの共通点、相違点
看護診断プロセスを理解するうえで必要となる知識
看護診断のプロセス
妥当性の高い看護診断を行うためのアセスメントのポイント
妥当性の高い看護診断を行う必要性
看護診断ラベルを理解するためのポイント
第4章 看護診断の実際
入院時の看護診断プロセス
入院中に生じた問題に対する看護診断のプロセス
付録1
付録2
目次
第1章 看護診断の考え方
第2章 看護過程の確認(看護過程の概要;「アセスメント」→「診断」における思考プロセス)
第3章 看護診断の理解(看護過程と看護診断;看護診断プロセスを理解するうえで必要となる知識;看護診断のプロセス;妥当性の高い看護診断を行うためのポイント;看護診断名を理解するためのポイント)
第4章 看護診断の実際(入院時の看護診断プロセス;入院中に生じた援助が必要と思われる対象の状態・状況に対する看護診断プロセス)
付録
著者等紹介
滝島紀子[タキシマノリコ]
千葉大学教育学部(特別教科看護教員養成課程)卒業。明星大学人文学研究科教育学専攻修了。東京大学医学部附属病院、杏林大学医学部付属看護専門学校、日本赤十字看護大学、東海大学健康科学部看護学科を経て、川崎市立看護短期大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。