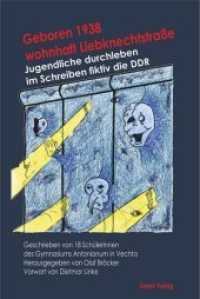- ホーム
- > 和書
- > 医学
- > 医学一般
- > 医療経営・管理・施設
出版社内容情報
《内容》 臨床検査は疾患の診断、予後推定、治療方針の決定、治癒判定などに不可欠である。さらに予防医学的には、潜在疾患の早期発見、健康診断などにも広く利用されている。誤った検査結果や検査室のサービス低下は、臨床医による誤診や診断の遅れに直接つながる。医療界においても品質マネジメントシステムの導入の必要性が大きくクローズアップされてきた。わが国でも、産業界で認定事業に実績を有する(財)日本適合性認定協会(JAB)と産官学共同体として臨床検査の標準化に実績を有する(NPO)日本臨床検査標準協議会(JCCLS)が共同で、わが国では初めてのISO 15189に基づく臨床検査室認定プログラム(Clinical Latory Accreditation Program :CLAP)を開発し、2005年8月より認定事業を正式に開始した。 本書は、過去2年間のCLAP開発委員会の活動を基に、ISO 15189の解説と認定審査における要求事項についてまとめたものである。
《目次》
はじめに
I章 適合性評価制度と臨床検査室認定制度
II章 ISO/TC212の活動とISO15189の誕生
III章 臨床検査室の認定手順
IV章 ISO 15189の解説と適用指針
序
1 適用範囲
2 引用文書
3 用語と定義
4 マネジメント要求事項
4,1 組織とマネジメント
4.2 品質マネジメントシステム
4.3 文書管理
4.4 契約の内容の確認
4.5 委託検査室による検査
4.6 外部からのサービス及び供給品
4.7 アドバイスサービス
4.8 苦情処理
4.9 不適合の識別と管理
4.10 是正処置
4.11 予防処置
4.12 継続的改善
4.13 品質及び技術的記録
4.14 内部監査
4.15 マネジメントレビュー
5 技術的要求事項
5.1 要員
5.2 施設及び環境条件
5.3 検査室の機材
5.4 検査前手順
5.5 検査手順
5.6 検査手順の品質保証
5.7 検査後手順
5.8 結果報告
6 附属書A(規範文書),
附属書B(参考文書),
附属書C(参考文書)
V章 特定の要求事項 ― 詳細の解釈及び指針
1 検査方法の妥当性確認
2 測定のトレーサビリティ(含JCTLMの活動)
3 不確かさの推定
4 技能試験
おわりに
付録A 臨床検査室の認定範囲分類
付録B JCTLMが国際標準と認めた標準物質一覧表
付録C 不確かさの推定法
付録D 認定機関概説
付録E ISO/TC212開発規格一覧表
内容説明
臨床検査は疾患の診断、予後推定、治療方針の決定、治癒判定などに不可欠である。さらに予防医学的には、潜在疾患の早期発見、健康診断などにも広く利用されている。誤った検査結果や検査室のサービスの低下は、臨床医による誤診や診断の遅れに直接つながる。医療界においても品質マネジメントシステムの導入の必要性が大きくクローズアップされてきた。わが国でも産業界で認定事業に実績を有する(財)日本適合性認定協会(JAB)と産官学共同体として臨床検査の標準化に実績を有する(NPO)日本臨床検査標準協議会(JCCLS)が共同で、わが国では初めてのISO 15189に基づく臨床検査室認定プログラム(CLAP)を開発し、2005年8月より認定事業を正式に開始した。本書は、過去2年間のCLAP開発委員会の活動を基に、ISO 15189の解説と認定審査における要求事項についてまとめたものである。
目次
1章 適合性評価制度と臨床検査室認定制度(ISO 15189「臨床検査室―品質と能力に関する特定要求事項」が目指す臨床検査室;適合性評価制度と日本適合性認定協会の役割)
2章 ISO/TC 212の活動とISO 15189の誕生(ISO/TC 212の活動;ISO 15189:2003の誕生(作成経緯))
3章 臨床検査室の認定手順(設定の基準及び条件;試験所認定の手順)
4章 ISO 15189の解説と適用指針(適用範囲;引用規格 ほか)
5章 特定要求事項の解釈(検査方法の妥当性確認;測定のトレーサビリティ ほか)
著者等紹介
河合忠[カワイタダシ]
1955年北海道大学医学部医学科卒業。1956~1962年米国留学(ハワイ州ホノルルクワキニ病院インターン、フロリダ州マイアミ大学医学部・ジャクソン記念病院病理学教室レジデント、米国解剖病理学/臨床病理学専門医(AP&CP))。1963~1967年国鉄中央鉄道病院(現・JR東京総合病院)検査科副医長。1964~1967年順天堂大学医学部非常勤講師。1967~1972年日本大学医学部臨床病理学助教授。1972~1974年同上臨床病理学教授/駿河台日大病院検査科部長。1974~1997年自治医科大学臨床病理学主任教授・附属病院臨床病理部長。(財)地域社会振興財団へき地生態科学研究所副所長。1997年~現在、自治医科大学名誉教授・国際臨床病理(ICP)センター所長。学会関係(現在)、国際標準化機構(ISO)TC 212国内検討委員会委員長、(財)国際医療技術交流財団理事長、(財)日本適合性認定協会(JAB)臨床検査室認定技術委員会委員長など。賞罰、第8回電気泳動学会賞(児玉賞)、第10回日本翻訳文化賞、日本医師会最高有功賞、世界病理学/臨床検査医学会連合最高有功賞「金の杖」賞、ドイツINSTAND最高有功賞「金の指輪」賞、第49回保健文化賞(日本厚生労働大臣表彰)、公益信託臨床検査医学研究振興基金第1回藤田光一郎賞、日本臨床検査医学会第1回功労賞など
青柳邁[アオヤギツトム]
1966年東北大学工学部金属材料工学科卒業。1968年同大学院修士課程修了(金属材料工学専攻)。1968年富士製鉄(株)(現・新日鉄)入社(製鋼技術室長、工場長等を歴任し、間品質管理、工場生産管理及び製鋼技術の開発の中で品質管理の実践を行う)。1994年~現在、(財)日本適合性認定協会試験所認定部(2002年から臨床検査室認定の企画・開発に携わり、2005年8月に臨床検査室の認定制度を立ち上げた)。学協会関係、国際試験所認定協力機構認定技術委員会委員、アジア・太平洋認定協力機構技術委員会委員、日本臨床検査標準協議会評議員、ISO/TC 212国内検討委員会TC1委員、WG1委員、国際計量研究連絡委員会物質量標準分科会委員、日本学術会議標準研究連絡委員会標準物質小委員会委員、(社)日本分析化学会分析信頼性委員会技能試験専門委員会委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 雪王の元へ