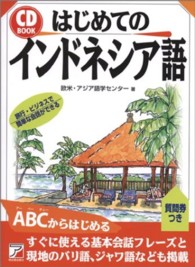内容説明
なぜモノは壊れるのだろう?物質はなぜそれなりの強度をもっているのだろう?かのファラデーをも悩ませた、材料強度に関する現象は、日用品から大型構造物の安全性や寿命などに多大な影響を与える。それにもかかわらず、応力集中などの知識は専門技術者の間でさえ定着していない。本書では、金属や木材、セラミックス、ガラス、骨などの強度は互いにどう関係しあっているのか、そしてこのような材料がさまざまな構造物―建物、橋、船舶、航空機、乗用車など―のなかでどのようにふるまうか、なぜそのようにふるまうか、といった事柄を扱う。工学系はもちろん、理学系で実験に携わる人には必読の書。
目次
ものの強さを科学する―人を困らせる、やっかいな質問の数々
第1部 弾性と強さの理論(応力とひずみ―なぜあなたは床を突き抜けて落ちないか;凝集力―物質は本来どのくらい強いはずか;亀裂と転移―なぜものは弱いか)
第2部 非金属はどのように使われてきたか(亀裂を止める―強靱であるためには;木材とセルロース―木造帆船を操った鉄人たち;接着剤と合板―木製飛行機の盛衰;複合材料―ワラ入りレンガから強化プラスチックまで)
第3部 金属はどのようにつかわれてきたか(金属の延性―転位の密やかな生態;鉄と鋼―産業革命の光と陰の源泉;これからの材料―あるべき姿を再考する)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まめタンク
2
2019年290冊目。すご〜く知的な人向けのニャリとする科学解説本です。2019/11/23
Sumiyuki
2
材料工学を数式を使わずに説明した本。2017/04/29
たい
2
材料の性質(剛性、強度、靭性など)を、歴史を紐解きながら、豊富な実例と著者の実体験を添えて、数式を使わずに解説している。解説は非常に丁寧で、そのわかりやすさはサイモン・シンのそれに匹敵するかも。また文章は教養とウィットに富んでいるので、読んでいて退屈しない。著者の経歴からか、木材とプラスチックの性質について多く述べられているのも特徴的。総合すると、理工系図書の中では稀に見る素晴らしい本。有名じゃないのは、材料科学という、一見地味に見える分野の話だからだろうか。2011/03/18