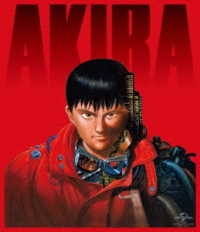出版社内容情報
コロナ禍、気候変動、ウクライナ戦争、ガザ紛争など、人間社会はますます危機に瀕している。なぜ、人間はこんな世界にしてしまったのだろうか。半世紀以上、ゴリラと向き合い、研究してきた霊長類学者の著者が、「ゴリラの目」で現代社会を見つめ直す。
内容説明
わたしたちの祖先は平和で平等を希求する社会を作っていたはずなのに、何が人間を間違わせたのか。ゴリラのまなざしで検証する、世界的霊長類学者による、未来へのメッセージ!
目次
第1章 ゴリラの国の歩き方(「闇の奥」で見たひかり;誤解と偏見 ほか)
第2章 ゴリラの家族(ゴリラの老いは美しい;タイタスの老年期 ほか)
第3章 暴力の起源(美徳と道徳の違いを超えて;暴力の起源 ほか)
第4章 サルの国(サルから見たリーダー論;ゴリラから見た人間社会の未来 ほか)
第5章 自然が語ってくれるとき(人類の終末と物語の消滅;パティ、おまえってやつは! ほか)
著者等紹介
山極寿一[ヤマギワジュイチ]
1952年東京都生まれ。霊長類学・人類学者。京都大学理学部卒、同大学院理学研究科博士後期課程単位取得退学。理学博士。83年に財団法人日本モンキーセンターリサーチフェロー、京都大学霊長類研究所助手、京都大学理学研究科助教授、教授、京都大学総長等を経て、総合地球環境学研究所所長。アフリカの奥地で40年を超える研究歴を有し、ゴリラ研究の世界的権威(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mae.dat
268
人間が築き上げてきた社会システムと、元来ヒトが持ち得た本能的な営みが乖離してしまっていると感じる今日この頃、皆様におかれましては如何お過ごしでしょうか。そのまま真に受けない迄も示唆に富んでいて。全部は語れないよ。ゴリラを中心とした現生霊長類の行動や太古の人類の歩みから、現代人が如何に争う様になったのかの考えは山極せんせーらしいですね。現在、インターネットに依るコミュニケーション革命に依って、集団間の境界が消失。自らのアイデンティティを確かめる為に、親しい仲間を蹂躙している。としているのは、中々ですね。2025/02/18
trazom
113
ゴリラを通じて、家族・共同体・暴力などを考えるとても示唆に富む一冊。食は個体本位、性は大っぴらな筈なのに、食は社会的、性は家庭内で秘匿という人間の共同体の特殊性。暴力の起源は、狩猟ではなく、農耕と定住で強いられた共同体への帰属意識である。「血縁関係もない人々によって作られた国家に忠誠を誓い、国家間の争いに命を懸けて参加する。これほど不思議で自然に反した行動はない」とのゴリラ学者の叫びがある。ゴリラのドラミングは威嚇ではなく、戦わずに面子を保って引き分けるための知恵だと言う。ゴリラを見習うことが沢山ある。2024/11/05
けんとまん1007
55
山極先生の本は、いつ読んでも、興味深く楽しく、知的刺激に溢れている。ゴリラ社会のありようを知るにつれ、そこに沢山の生きるヒント・方向性を見出すことができる。自然の一部として生きることと、テクノロジーが変化し続ける中で、どう折り合いをつけるのかを考える。一極・一点に集中するのではなく、複数の視点を持つこと、互いに譲り合いながら、かつ、頼り頼られること。そんなこを思う。少し我慢が必要な時もあれば、多少の我儘でもいい時もある。おたがいさまの精神だろうと思う。2024/12/07
クリママ
42
たった一人で刺されると猛烈にかゆくなる虫が山ほどいるアフリカの熱帯雨林の中を毎日数時間歩いてゴリラの群れに会いに行き、ゴリラとともに生活する研究者に驚く。ゴリラの生態、ヒトとゴリラの進化の過程の違い、暴力の起源を探る。それはとても興味深い。ヒトは強い共感力を持ち、特定の相手を大切にする。だから「自分をしっかりと持って、相手と少し距離を置く。…そうすれば敵も味方もつくらず、争いも起きません。」そうなのか。今も、戦争内紛のような大量殺戮を繰り返す人間。怖ろしい指導者。私には表題の意味を読み取るのは難しかった。2024/12/29
ブルちゃん
35
めちゃくちゃゴリラに興味わく。この間の絵本でも見たが、シルバーバックのオスのリーダーの好感度がまたup笑 しかしパティの話にはびっくり。類人猿と人間の進化や暴力性や子育てなど、多面的な視点からのお話が、すっごく勉強になったり、少し難しかったり。繰り返し伝えてくださる部分は、こんな私でも知識として残る✨たくさんの貴重なお話が聞けて良かったです😍2025/01/15