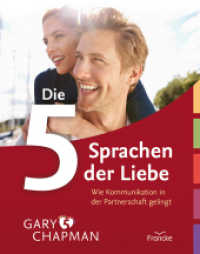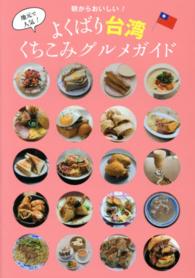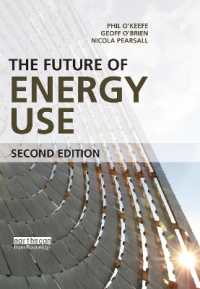内容説明
先代、父梅幸、二代松緑、十七代勘三郎…歴代名優との共演、女方中心の若手花形から立役への転換、音羽屋の伝統を継承しつつ独自のスタイルを開拓し続ける円熟期まで、その芸の神髄に迫る。
目次
序 尾上菊五郎
第1章 俳優の自覚
第2章 稽古は苦にしない
第3章 芝居の命
第4章 芸の道には本当も嘘もない
第5章 果てなき道
著者等紹介
小玉祥子[コダマショウコ]
演劇ジャーナリスト。1960年東京生まれ。青山学院大学経済学部卒(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
旅するランナー
181
「歌舞伎の持つ独特の形式美、そういうものと色気、艶、愛嬌、江戸っ子気質などを研究してお客さんに楽しんで頂ける役者になりたい」2021年の文化勲章受章の際にそう語る。俳優として1948年にスタートして舞台生活75年越えてなお「この仕事に終わりはない」と口にする。妻富司純子、長女寺島しのぶ、長男菊之助。これまで演じてきた役それぞれへの言及や、1966年NHK大河ドラマ「源義経」主演と東映スター女優富司純子との共演による出会いエピソードなど、内容が充実してます。2024/05/18
takao
1
ふむ2024/11/27
etoman
1
ここ何年か、菊五郎が歌舞伎座や国立劇場で出ている作品の多くを観ているのだが、立役専門になった後からなので女形は多分一度も観てない。女形時代の菊五郎を観たかった。まだまだ菊五郎の舞台を観ていたいので、元気にいてもらいたいものです。2024/02/13
rinrinkimkim
1
成田屋襲名披露公演のお供。一代記であり芸談。鏡獅子の二枚扇はギアをあげる。とか弁天のタバコ葉を入れる、火をつけるも全て決まったタイミング、塩谷判官の声は師直がさらに高音で言うので(フナ侍ですね)低音で。また襲名挨拶は日時を知らせないのが慣習。対面できるまで何度でも通う。ひえー!成田屋13代目もそうしたの?梅幸の弁天は美人局、菊五郎はふてぶてしい不良。と2代松緑が絶賛。などお芝居ではなくお芝居する人側のお話がいっぱい!純子ママが恋人時代の電話は「富士銀行からです」と繋がれたらしい。かわいい。長生きしてね!2024/02/13
hidehi
0
「芸談」というよりは「私の履歴書」的な自伝の趣の方が強いかな。もともと微に入り細に入り言語化するような芸質の人ではないように思うので、まぁ仕方ないかなぁ。この人はいつまでも元気に動いて主役をやり続けてくれるような気がしていたが、やはり年齢には抗えず…(それは現白鵬も同じ。。)七代目菊五郎さんのほぼ全盛期を、十二代目団十郎や二代目吉右衛門、九代目幸四郎といった盟友・ライバルとの切磋琢磨と共に目撃できたのは幸運だったと思う。2025/01/31