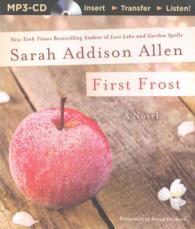目次
知覚・認知心理学とは―考えることの科学
知覚・認知心理学の研究法―「考えること」をいかに科学するか
知覚・認知の神経的基盤―脳が考える
感覚の科学―感じるしくみ
知覚のしくみ1―モノが見える不思議
知覚のしくみ2―意識にのぼる世界とは
注意と認知―限られた資源を生かす
記憶のしくみ1―記憶と神経的基盤
記憶のしくみ2―日常記憶
問題解決―山頂を目指すには
判断と意思決定―人間は合理的か
推論―論理的に考える、一から十を知る
クリティカルに考える―信じる心、見抜く心
認知と発達―推論する心、共感する心
認知と感情―悲しいから泣くのか
著者等紹介
石口彰[イシグチアキラ]
1955年群馬県に生まれる。1988年東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。現在、お茶の水女子大学基幹研究院教授・文学博士。専攻は認知心理学、人間情報学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
himajin315
2
知覚・認知はある程度わかるかな〜って思って読んだけど、結構難しい本だった。忘れた頃にまた読み返したい2023/01/22
brawi
2
クリティカル・シンキングは論理的思考をベースに批判の目を自分と他者との「双方の思考」に向けることがポイントになる。(p228)が印象に残った。 本全体は最初は知覚(五感)について神経細胞における電気信号の伝達、神経伝達物質のイオンにより電位が発生する事、中・後半は認知について諸々の事が書いてある。人間は損に敏感とか経済心理学的なことも書いてありおもしろい。統計に騙されやすいとか。2019/12/28
リリパス
1
例えば、脳の情報処理システム、失語症、活動電位、ブロードマンの脳地図、色覚多様性、ハイパーコラム、視覚失認、パンデモニアム理論、マガーク効果、選択的注意、特徴統合理論、バーナム効果、脳の機能の測定方法、ベキ法則、ベイズ統計、プロスペクト理論・・・などをもちいて、脳の記憶の仕組みや、日常生活で起きる出来事に関する感情が発生する仕組みなどを解説していますが、全体的に難しめな本でした・・・・・・。2020/10/16
ezura
1
情報科学科のカリキュラムで認知心理学を学んだことがあるが、それとは視点が異なり面白かった。2020/06/30
たけ
0
復習再読2025/05/02
-
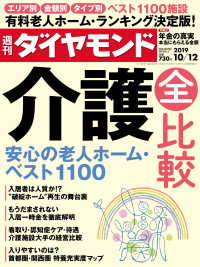
- 電子書籍
- 週刊ダイヤモンド 19年10月12日号…