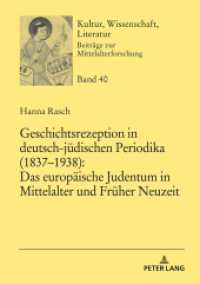目次
『古事記』の成立と歴史意識
神々の世界
大和王権の成立
反乱伝承の諸相
ヤマトタケルの物語
磐姫皇后像の形象
英雄時代の終焉
初期万葉の時代―額田王
分水嶺としての柿本人麻呂
和歌の変革者たち
東歌と防人歌
和歌の表現の本質―巻十六から
万葉歌の終焉―大伴家持
著者等紹介
多田一臣[タダカズオミ]
1949年北海道旭川市に生まれる。1975年東京大学大学院修士課程修了。現在、放送大学客員教授・二松学舎大学特別招聘教授・東京大学名誉教授。博士(文学)。専攻は日本古代文学・日本古代文化論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
内島菫
18
たまたま放送大学で聞いた「心は外にある」という古代の歌の世界がとても印象的だったので読んでみる。万葉集が古事記を引き継ぎ、古事記が日本書紀に配慮しているという書物間の照応が、ひとつらなりの宇宙を形成しているようで興味深い。歌によまれた、例えば雲は内面の比喩でもあり、もっといえば雲の形こそ心の形であり、さらには、万葉集の最後を飾る大伴家持の歌の、逆に風景と乖離した心、あるいは乖離しているからこそ切り開かれる心のその先は、確かに著者の指摘するように近代的な意味合いにおける人間の根源的な孤独へと繋がる。2023/02/08
オザマチ
14
各章でピックアップされる話題が非常に興味深く、講師の多田先生の話し方も明瞭で非常に分かりやすい講義だった。独力で『古事記』や『万葉集』について学ぶのは困難なので、少しでも興味があれば履修すべき。2018/07/08
hal
7
放送大学の教材。『古事記』と『万葉集』の概要と内容の一部抜粋をまとめている。ジャンルとしては、歴史ではなく古文のようだ。『日本書紀』が対外的な事情を考慮した歴史書であるのに対し、『古事記』は国内的に向けた文学的な歴史書とのこと。『古事記』は三巻に分かれ、上巻が神々の話(アマテラスやオオクニヌシ等)で、中巻が英雄談(ヤマトタケル等)で、この辺りまでは大体の内容は知っていたが、下巻の仁徳天皇から推古天皇あたりの話は初めて知りました。女兄弟が祭祀を担当し男兄弟を守るという考えがあったというのは興味深かった。2019/09/15
黒豆
5
古事記に記載されている話をもう少し詳しく知りたいと思い受講、そして、試験を受けてきました。神の代、神と人の代(神武天皇〜応神天皇)、人の代(仁徳天皇〜推古天皇)、とそれぞれ興味深い内容だった、富山県にゆかりの大伴家持が突然創作作を止めた理由が気なった。読み物としては面白いが試験となると??今期は、もう一つは新しい仕組みであるオンライン授業で「がんを知る」を受講、試験場での最終テストは無いが、途中で試験や意見を述べるようなレポートと従来法より倍以上時間を割き考えなければいけない講座だった。2016/07/30
SK
1
167*思ったよりも難しいというか、自分が想定していた内容とは違ったというか。2018/08/03