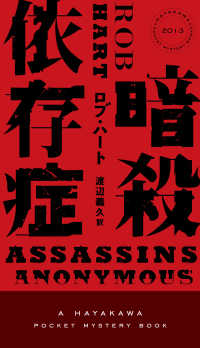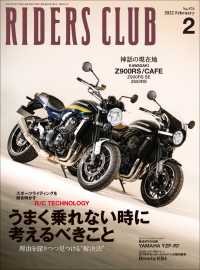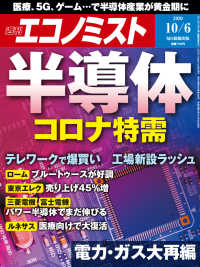目次
日本文化の基層―日本の風土、縄文と弥生、「内と外と」という視点(縄文・弥生・古墳時代)
日本文化の基盤形成―仏教伝来、天皇中心の国家体制、日本神話(飛鳥・白鳳時代)
古代の国家と古典―律令制国家、鎮護国家、『万葉集』(奈良時代)
日本化の始まり―平安遷都、日本仏教の形成、神道の成立(平安初期)
国風文化の展開―仮名と和歌、摂関制と物語、末法思想と浄土教(平安中期)
中世の始まり―隠者、『平家物語』、王朝古典主義(院政期・鎌倉初期)
鎌倉新仏教の成立―祖師たちの思想、元寇と神国思想(鎌倉時代)
新たな文化の展開―禅文化、能楽、各種芸道(南北朝期・室町時代)
日本社会と文化の革新―下剋上と一揆、西洋との出会い、全国統一と茶の湯(戦国時代・統一期)
近世社会の形成―幕藩体制、身分制と家、流派武芸、「鎖国」(江戸初期)〔ほか〕
著者等紹介
魚住孝至[ウオズミタカシ]
1953年生まれ。1983年東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学、国際武道大学教授を経て、放送大学特任教授。博士(文学)。専攻、倫理学、日本思想、実存思想(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
190
知識の羅列が続くので単調に感じられたが、面白い話も幾つかあった。具体的な像を持たぬ神道に比べ仏教が国家統治に必要だったこと。像の力に加えて聖徳太子の三経義疏では古註釈を参照しながら普遍的な真理を探究したこと。その執筆中に隋が高句麗に敗れ(やがて滅び)、太子の政治的立場が危うくなっていったこと。芭蕉の「野ざらし」の旅の実際的な面と風狂の面という話や、後年、自らの集大成となる「おくのほそ道」の旅でも実際の出来事に虚構を交えて五部構成に仕上げていく、という話はよかった。残念ながらラジオの万葉集の音読は酷かった。2023/04/19