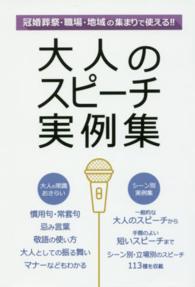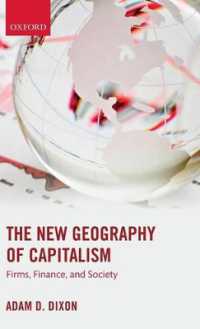内容説明
プーチンはなぜ「神の代理人」として振る舞えるのか?「力」か「自由」か―歴史の変革時に常に「力」を選び続けてきたロシアの風土をロシア正教会の歴史からたどる本邦初の意欲的な試み。
目次
第1章 「ルーシの世界」のはじまり
第2章 キエフ・ルーシの改宗
第3章 統治者は「地上における神の代理人」たりえるか
第4章 「ロシア」の誕生
第5章 ウクライナの誕生
第6章 宗教的原理主義の行方
著者等紹介
三浦清美[ミウラキヨハル]
1965年(昭和40)、埼玉県生まれ。早稲田大学文学学術院教授。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。博士(文学)。サンクトペテルブルク国立大学留学。専攻はスラヴ文献学、中世ロシア文学、中世ロシア史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





ヒロの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
塩崎ツトム
20
なぜロシアは皇帝が神権より上位につくのかというのを、政治制度とは別に、キリスト教の受容と、そしてナショナル・アイデンティティの形成の過程を建国の歴史と絡めわかりやすく説明。なるほどこういう思考かと理解できるが、ウクライナと如何にしてアイデンティティが分かれたかについても解説しているので、やはりロシアとウクライナは別の国であり、そもそも10世紀くらいに形成されたお題目で他国を蹂躙されちゃ困るのである。2025/01/13
田中峰和
6
なぜ世界中の反対を無視してウクライナ侵攻を続けるのか。ユダヤ教とカトリック、正教、イスラム教など当時の宗教と国家に遡って、解説される内容は教科書の何倍も詳しく興味深い内容だった。ロシア人の思考回路を知るにはうってつけの良書だ。ロシア正教会のキリル大司教は「プーチンがロシアを統治するよう神によって定められている」と主張する。民族的に遅くキリスト教に改宗した劣等感は西欧NATOへの対抗意識となり、ウクライナが加盟することを許容できない。そして国民の統治者観は、絶対的な力をもつ神の代理人に委ねる意識が根深い。2023/01/16
shimashimaon
6
キリスト教関係の読書が役に立ちました。新約聖書にある「ぶどう園の労働者」の例えの如く、遅れて改宗したロシアが先頭に立つべく、テオーシスを体現するアウトクラトール(神の代理人)であるツァーリを希求する。ローマ教会と異なり東方正教では民族固有の言語による布教が行われ、世俗権力に果敢に対抗する宗教者も出現した。キュリロス・メトディオス兄弟、トゥーロフのキリルetc.。信仰は凄い。モンゴル侵寇という歴史に根ざすリアルな終末論とテオーシスに基づく自力本願的要素の濃さが、「回路」の特徴でありそうなことを垣間見ました。2022/11/15
takao
3
ふむ2024/06/13
バルジ
3
「ルーシ」の歴史的淵源を同時代の文学作品から辿る他に類書のない新書。聞き慣れない固有名詞の嵐で中々読むのに骨が折れるが、現代ロシアの「古層」を窺い知るのに最適な一冊であろう。ロシア史に疎い評者はリューリク招請の理由が自らを統治してもらうために「招いた」点に驚く。その後のキリスト教受容の姿はむしろ「中心」への飽くなき渇望がありながら、「中心」たり得ない辺境国家の激しいアイデンティティのせめぎあいに見える。テメーシス概念やアウトクラトールはプーチニズム理解の一助にもなる。2023/02/11
-
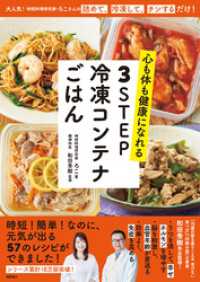
- 電子書籍
- 心も体も健康になれる 3STEP 冷凍…