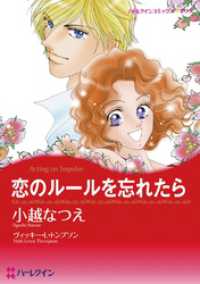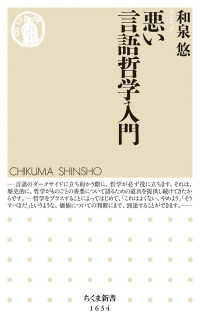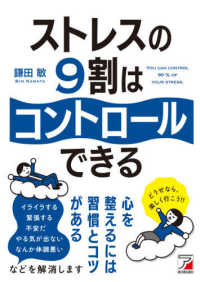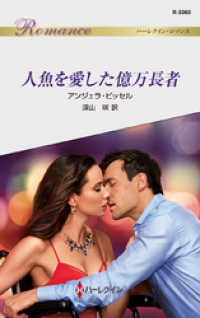出版社内容情報
【辛く悲しい思いは遠くにおしやり、空いたところに心地よい「何か」をコピペする】
新進気鋭のデカルト研究者による、心が晴れる「哲学書」!
抑えきれないマイナスの感情を上手にコントロールし、穏やかに鎮めていく確実な方法を、デカルトが易しく伝授!
◎「感情をコントロールするにはどうすればよいか、それをデカルトとともに考えていきます」――著者
【本書の内容】
悲しくなったら思い出すことを決めておく/人はなぜ同じ状況下でも異なった感情を持つのか?/「最も偉大な魂」と「卑しく凡俗な魂」の違い/「過度な驚き」は無知を改善しない/デカルト的「散歩の効用」/「何も考えずに」精神を休ませる/「想像力」の酷使は「一日のうちごく僅かな時間」に/何時間も平気で続く会議はボイコットせよ/悲しみも憎しみも「身体」と「健康」に有益/怒り心頭で平手打ちを喰らわせてしまいそうな時/人生において心地よい気分をじっくりと味わうために/「森のなかで道に迷った旅人」はどうするか?/自分の力ではどうにもならないことは諦めろ!/人はどのような理由で自分を重んじることができるか/最も高邁な人たちは、最も謙虚な人たち/人は生まれつき何かを愛するようにできている/非の打ち所がない美男美女には飽きてくる?/愛は人を「過激派」にする!?/悲しみや苦しみは「少しずつ」解消する/どうすれば「最も堪えやすい」視点から出来事を眺められるか/「喪失」を埋める一つの方法/「謙虚な生き方」を自分のものにせよ/感情に振り回されて後悔しないための方法/信頼できる人の行動や意見を参考にする/心の平安のために必要な「安全装置」/「理性」を最大限に駆使して「最も」合理的な選択をせよ!/「どのような悪に見舞われても」もたらされる達成感と満足感/雨にも風にも負けない生き方とは?/「初志貫徹」と「臨機応変」を両立させよ!/「正解」も「不正解」もなく、あるのは「考える」ということ
【著者紹介】
津崎良典(つざき・よしのり)
1977年生まれ。国際基督教大学(ICU)教養学部人文科学科卒業。大阪大学大学院文学研究科修士課程修了。パリ第一大学パンテオン=ソルボンヌ校哲学科博士課程修了、哲学博士号を取得。現在、筑波大学人文社会系准教授。共著に『よくわかる哲学・思想』(ミネルヴァ書房、2019年)など、共訳書に『デカルト全書簡集』第4巻(知泉書館、2016年)、『ライプニッツ著作集』第2期第2巻・第3巻(工作舎、2016年・2018年)、ブロック『唯物論』(白水社・文庫クセジュ、2015年)、デリダ『哲学への権利』第2巻(みすず書房、2015年)、ネグリ『デカルト・ポリティコ』(青土社、2019年)などがある。
内容説明
辛く悲しい思いは遠くに押しやり、空いたところに心地よい「何か」をコピペする。新進気鋭のデカルト研究者による、心が晴れる「哲学書」!
目次
デカルトは想像力で「癒す」
デカルトは冷静に「驚く」
デカルトは意外と「休む」
デカルトはしみじみと「感情を味わう」
デカルトは穏やかに「暮らす」
デカルトはたっぷりと「自分の能力を使いきる」
デカルトは検証して「愛する」
デカルトは少しずつ「慰める」
デカルトはいつか「死ぬ」
デカルトは遠大に「準備する」
デカルトはできる限り「助け合う」
デカルトは三叉路で「迷う」
著者等紹介
津崎良典[ツザキヨシノリ]
1977年生まれ。国際基督教大学(ICU)教養学部人文科学科卒業。大阪大学大学院文学研究科修士課程修了。パリ第一大学パンテオン=ソルボンヌ校哲学科博士課程修了、哲学博士号を取得。現在、筑波大学人文社会系准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
ピラミッド