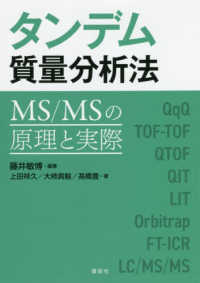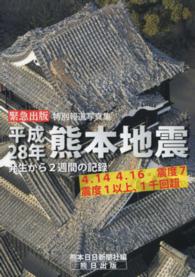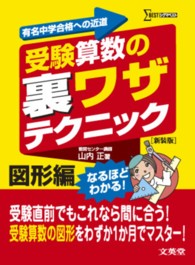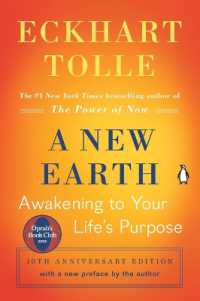出版社内容情報
【いじめは1980年代から大きな社会問題となり、悲劇が続いている。ブラック勤務とも言われる厳しい勤務状況の中、教職員など教育関係者たちも必死に対策を練ってきた。だが何かが足りなかった。そう言わざるを得ない。
足りないのは何なのか。教育専門家でも文科省職員や学校関係者でも何でもない一人の父親、一人のテレビ局記者・ディレクターでしかない私だが、そろそろ私のような第三者による“外野の声”にも耳を傾けてみてほしい―】(「はじめに」より抜粋/※予定)
小中高校で認知されたいじめの件数、過去最多(2022年度)。心身に重大な被害が生じるなどの疑いが認定された「いじめの重大事態」の件数、過去最多(同)。
我が子を守るために、いま大人が知るべき実態と予防策。
いじめの原因は、スマホ依存、ブラック部活、教員のブラック勤務、偏る食事習慣……だった?
“いじめが始まる前に防ぐ方法”を、20年以上にわたりいじめ問題を取材し続けるTBS記者が徹底ルポ。
*プロフィール
川上敬二郎(かわかみ・けいじろう)
1973年、東京都出身。1996年にTBS入社。ラジオ記者、報道局で社会部記者、『Nスタ』、『NEWS23』、『サンデーモーニング』などでディレクターやデスクを経て、現在『報道特集』ディレクター。これまでに「スマホ依存の子どもたち」、「教員の?ブラック勤務”問題」、「ネオニコ系農薬 人への影響は」、「有機農業の未来は?」などを放送。「貧困ジャーナリズム大賞2022」特別賞(共同受賞)。映画『サステナ・ファーム トキと1%』(TBSドキュメンタリー映画祭2023「国際有機農業映画祭」招待作品)を初監督。2003年には「米日財団メディア・フェロー」としてアメリカ各地で放課後改革を2ヶ月間取材。帰国後、友人と「放課後NPOアフタースクール」を設立(2009年に法人化。グッドデザイン賞やキッズデザイン賞を受賞)。『子どもたちの放課後を救え!』(文藝春秋)などを出版。その後も子どもたちを取り巻く問題に関心を持ち、2019年6月ドキュメンタリー番組『ザ・フォーカス』で「いじめ予防」を放送。現在も取材を続け、TBS NEWS DIGで「いじめ予防100のアイデア」を連載中。
内容説明
やってはいるが、うまくいっていない。それが日本のいじめ対策の現状だ―。いじめ対策がうまくいかない原因は、スマホ依存、ブラック部活、教員のブラック勤務による見逃し、“いけない”というだけのワンパターンな指導…にあった!?20年以上にわたり取材を続ける報道番組ディレクターが、“いじめの発生や深刻化の予防法”を徹底ルポ。一人でも苦しむ子を減らし、その家族も教員も救うため、私たち大人が子どもと一緒にできることとは。
目次
第1章 いじめ問題の正体―現状と課題を読み解く(対策の“智将”森田洋司;「いじめ問題」との出会い;森田と「いじめの四層構造」 ほか)
第2章 これからのいじめ予防対策―いじめに巻き込まれる子どもたちをどう守るか(子ども・家庭;教員;学校;社会)
第3章 明日からできる効果のある「いじめ予防」授業(ドイツの最新いじめ予防授業;情報リテラシー教育の必要性;なぜ広まらない?世界トップクラスの予防策;北欧発の予防授業をやってみる;フィンランド発「キヴァ」を参考にした授業;“純潔主義”に訴えるだけの道徳を超えて;最後は「市民性教育」につきる;いじめが止まりにくい社会)
著者等紹介
川上敬二郎[カワカミケイジロウ]
1973年、東京都出身。1996年にTBS入社。ラジオ記者、報道局で社会部記者、『Nスタ』『NEWS23』『サンデーモーニング』などでディレクターやデスクを経て、現在『報道特集』ディレクター。「貧困ジャーナリズム大賞2022」特別賞(共同受賞)。TBSドキュメンタリー映画祭2023で『サステナ・ファーム トキと1%』(「国際有機農業映画祭」招待作品)を初監督。2003年には「米日財団メディア・フェロー」としてアメリカ各地で放課後改革を2ヶ月間取材。帰国後、友人と「放課後NPOアフタースクール」を設立(2009年に法人化。グッドデザイン賞やキッズデザイン賞を受賞)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
活字の旅遊人
miyoga
広瀬研究会
takao
-

- 電子書籍
- 玉佩輪廻~この陰謀、死に戻りで制します…