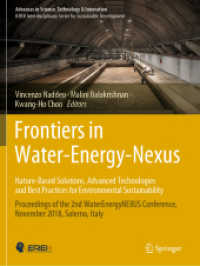出版社内容情報
渋沢栄一は「日本資本主義の父」と呼ばれ、新しい1万円札の顔にも選ばれました。日本初の銀行をはじめ、現代も日本社会を支える数多くの大企業を創設するなど、その功績は新しいお札にふさわしいです。しかし、渋沢栄一の魅力は、経営者としての成功だけではなく、常に世のために生きるという道徳心に貫かれた生きざまにあります。激動の時代を迎える今こそ知っておきたい、日本が誇る偉人の半生を楽しいコミックで伝えます。
内容説明
怒濤の幕末を駆け抜けた、「日本近代資本主義の父」の物語。
目次
第1章 血洗島のからっ風
第2章 志士の団結
第3章 一橋慶喜公のもとで
第4章 欧州見聞録
第5章 虹の向こう側へ
渋沢栄一を知るための基礎知識
著者等紹介
加来耕三[カクコウゾウ]
歴史家・作家。1958年、大阪府大阪市生まれ。1981年、奈良大学文学部史学科卒業
後藤ひろみ[ゴトウヒロミ]
ふくい歴女の会会長。福井県立歴史博物館併設カフェ代表。福井県福井市生まれ。福井高専卒。開催に携わった2014年の歴史研究会全国大会をきっかけに、深く歴史に魅せられる。歴史研究会会員
中島健志[ナカシマタケシ]
福岡県福岡市生まれ。九州産業大学卒業。1988年、『コミックアフタヌーン3月号』(講談社)に「中尉殿の飛燕」(’87冬季賞受賞作)が掲載され、漫画家としてデビュー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
30
『論語と算盤』らしく、論語を勉強(7頁)。渋沢家は藍玉製造販売で取引の帳簿、まさしく算盤勘定をこなす商才が求められた(10頁)。『論語』は日本人が初めて手にした書物とのこと(12頁)。1869年(明治2年)、栄一は日本初の合本会社「商法会所」を設立(88頁)。民が中心に(89頁)という主張は福澤諭吉先生と同様だ。同時代人であった。1871年いとこで恩師の尾高惇忠を富岡製糸場初代場長に任命(91頁)。金融界から引退した1916年(大正5年)、『論語と算盤』9月に出版(加来耕三、114頁~)。 2021/09/04
たまきら
30
今度一万円札でお顔を合わせることになるだろうし、娘さんと一緒に勉強しておこうかな…と。財閥と距離を置く生き方は鮮烈で、激動の時代を切り開いた人々にふさわしい凛とした存在感が感じられました。お札的には娘さんは聖徳太子の復活を期待しているもよう。彼女の聖徳太子へのリスペクト、半端なし。…山岸涼子さんの名作デビューも間近か。現在の一万円札男子はじいじのでた大学を作ってるよと誘ってみたが、まったく興味を持たず。まあいつかそのうちに。津田梅子さんを楽しんだだけでも良かったかな。2021/06/30
零水亭
15
よく分かりました。2021/06/04
nbhd
14
感銘を受けたのは、渋沢栄一がパリを訪問した際の気づきだ。僕なりに言葉を置き換えると、きっと渋沢さんは次のように驚いたことだろう→①「アレ??商人も軍人も、なんか対等に会話するんだな、士農工商みたいな身分制度がないのか、すごっ!」、②「なにその”バンク”っていうのは!一か所にお金を集めて、いろいろ使い回すの?えっ、株式会社って、なにそれ!日本にも商売人で金持ちはいるけど、みんなでお金を出し合って何かしらの事業をおこすってことでしょ、すごっ!」。人生が塗り替わるような衝撃だったんだろうなぁ。2024/07/22
あやほ
4
渋沢栄一の生涯をざっと知るにはよかった。 “衣食足りて礼節を知る、貧すれば鈍す” もっと渋沢栄一について知りたいと思えた。2021/11/26
-
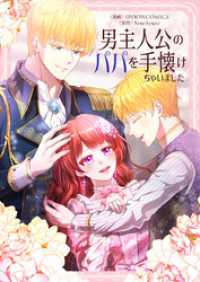
- 電子書籍
- 男主人公のパパを手懐けちゃいました【タ…