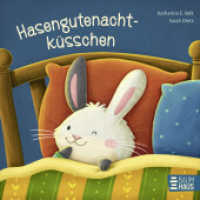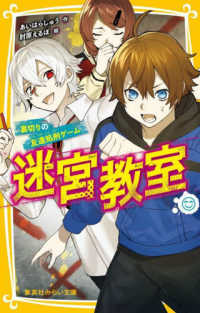出版社内容情報
大きな体とふしぎなひれをもつ魚・マンボウを追う研究者が、水族館で研究開始! マンボウの魅力いっぱいのノンフィクション。
内容説明
2017年、マンボウが世界に3種いることを海外の共同研究者とともに突きとめた「マンボウ博士」こと澤井悦郎さん。博士がえらんだ次の研究の舞台は…みんな大好き「水族館」!?マンボウの本当のすがたを追い求める、ゆかいでおどろきいっぱいの水族館レポートです。
目次
第1章 わたしがマンボウ博士になるまで
第2章 カクレマンボウを公表せよ
第3章 マンボウ属は3種いる
第4章 水族館は「生きた博物館」
第5章 マンボウ飼いたいんですけど
第6章 水族館で、新しいマンボウ研究が始まった
第7章 マンボウは上を向いてねむるのか
著者等紹介
澤井悦郎[サワイエツロウ]
1985年生まれ。農学博士。幼いころからマンボウの魅力にとりつかれ、広島大学で研究を始める。ウシマンボウとカクレマンボウの名付け親。現在は分類学、生態学、民俗学などさまざまな視点からマンボウを研究中。サークル「マンボウなんでも博物館」で創作活動も行い、イベントに積極的に参加している。2013年岩手県三陸海域研究論文(学生の部)岩手県知事賞受賞。論文ナビ主催2018年研究アウトリーチ大賞受賞。2019年度日本魚類学会論文賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
mae.dat
96
マンボウは研究途上と言うより、やっと始まったって感じなんですかね。 本当にまだまだ未知で、解き明かす事がいっぱいある様に思われます。 マンボウを飼育するにあたり、成る程と思ったり、驚きの工夫などが施されているのですね。 生態や行動を解明すると共に、より傷つかずに水族館で飼育できる方法を確立して欲しいと願います。 博士になるには、「好奇心と引きかえに、ある程度人生を捨てる覚悟が必要」って言葉は、決して軽く無い。2020/07/26
☆よいこ
78
児童書。マンボウの研究をしている著者が、マンボウについて熱く語る。ここ10年くらいでわかったマンボウの分類(新発見)についてと、マンボウの生態がわかりやすい。まだ研究途中で、論文発表もされていない事実をここまで書いていいものか~と思えるくらい、親切に説明しているが「誰でもできるコトだけど、誰もやろうとしない研究を真面目にやる」のが研究者なんだね。マンボウへの愛情と、水族館の魅力を感じられる一冊。▽スペシャルサンクスに、マンボウ死んでるPがあったのに本文にはなかった。BGM参加なのかしらん。巻末に参考資料。2020/09/25
たんぽこ
10
マンボウへの著者の情熱をひしひしと感じる本でした。素人には難しい(ついていけない)部分もありましたが、面白かったです。水族館の飼育員には、研究に費やす時間はほとんどないので、研究を専門とする人が所属したり、他の機関の研究者と共同研究を行う機会を増やさなくてはいけないという著者の提言にはショックを受けました。水族館は学術機関だから専門家達が日夜研究に励んでいるのだとばかり思っていました・・。日本の研究環境の厳しさには気持ちが重くなります。2020/05/06
とかねね
6
最後のおわりにで「小学生であろうと手加減はしません」と書かれていた通り、児童向けにしては専門的な本でした。好きな子は好きなんだろうけれど...、読んではみましたが紹介するのは諦めました...。変わった魚だなぁと思ってはいましたが、マンボウのことはまだまだ謎が多いようです。マンボウのことがよくわかる、愛に溢れた一冊でした。2020/02/09
海星梨
5
図書館で絵本とか児童書とか漁って1時間くらい読んで帰る休日。うん。分類生物学は読んでてつまらない生物学1位だと思う。あと、タイトルの疑問は回収されてないタイトル詐欺でもある。児童書としの態度はいいんですが、生物学のあるあるタイトル詐欺系……。まぁ、観察とか実験とかが予定通りに行かなかったり、論文発表前に成果発表できなかったり、原稿料も生活に必要だからって事情はわかるんですが。2024/09/24