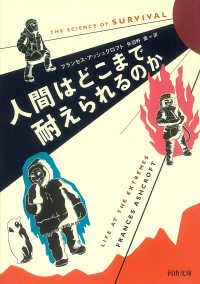出版社内容情報
子どもの可能性を型にはめるな! これからの知性は「答えのない課題」にどう向き合うか、教育の多様性を考える一冊。
内容説明
「平均的な底上げ」を得意とし、「年相応の学び」を提供してきた日本の学校教育。学歴社会が終焉し、人生の目的や価値観が多様化するなか、旧来の教育システムに柔軟かつ個性のある人材は育てられるのか。知性の深まり、「私と世界との関係」など、原点に立ち返り「学び」を論じる一冊。
目次
第1章 子どもと親が、学びの場所を選べる社会(学外教育支援に一筋の光;「教育機会確保法」策定の背景 ほか)
第2章 公教育か私教育か(ある中学生男子のエピソードから;習い事ブームの背景 ほか)
第3章 学びとは自分を知ること(大人は子どもの輝きを知らない;教育の原点は幼児教育 ほか)
第4章 求められる「資質・能力」とは(学びの原理と「資質・能力」;アクティブの本質とは ほか)
第5章 低成長時代の正しい弱さ(社会に出る水路、あるいは登り道;立身出世から銘柄学校へ ほか)
著者等紹介
汐見稔幸[シオミトシユキ]
1947年大阪府生まれ。東京大学教育学部卒、同大学院博士課程修了。現在、白梅学園大学学長、東京大学名誉教授。専門は教育学、教育人間学、育児学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Taka
47
最近は中学生の活躍が目立ちますね! 天才というより、日本には個性をより伸ばすための教育システムが必要なのだろうと感じました。2018/03/12
けんとまん1007
30
いろんな考え方、プロセスがあっていいと言うこと。確かに、日本のこれまでの教育は、基礎学力+型にはめる=知識という流れできたのだと思う。もちろん、それはそれで大切だと思うし、否定もしない。ただ、それだけでは、収まらない環境になってきたということがある。そのためには、より、柔軟な発想が必要。日本人は、あるものが流行ると、それだけに走ってしまうことが多い。そこで、1歩ひいて考えることが、最も重要だ。2018/09/04
りょうみや
15
「天才」を育てる教育とは、全ての人たちの持つ個性を上手に伸ばす教育ということで、今の日本の一斉教育を批判してオランダのような多様性のある教育を目指したいような旨の著者の教育哲学を語っている。個人的には分かりやすいようで実は分かりにくい内容だっった。2018/04/12
maimai
9
天才…自分の好きなことを追求して文明に多大な影響を与える人物。学校教育の中では教師の模範となる人物が評価されますが、実社会では自分の能力を用いて利益を生み出す人間が評価されます。経済的な行き詰まりをみせている日本社会においては教育方針を見直し子供の個性を追求する方式が見直されますが、自分が何が好きなのかを子供達自身が考える必要があります。単一的なレールをなぞれば明るい未来があるとされた時代は終わり、インターネットの普及により国際化が増す中で、自分の好きを追求して付加価値をあげる人に明るい未来があるのかな2020/09/09
ちい
9
タイトルに惹かれた。とても平易で読みやすい文章だった。2016年に策定された教育機会確保法が著者の大きなテーマでありキーワードであった。 本来学びは私的で自立していて、多様であった。今の学校制度は全員を担保しようとするあまり、画一的で窮屈である。2019/04/15