出版社内容情報
椎野 直弥[シイノナオヤ]
内容説明
当然、あるとは思っていた。入学式の日には当然これが、自己紹介があるっていうのはわかっていた。言える。言える。言える。言える。―言えない。その帰りに受け取った、部活勧誘の一枚のチラシに、僕は心をとらわれた。中学の入学式の日、自己紹介の場から逃げ出した悠太の葛藤と、出会いそして前進の物語。
著者等紹介
椎野直弥[シイノナオヤ]
1984年(昭和59年)、北海道北見市生まれ。札幌市の大学を卒業後、仕事のかたわら小説の執筆を続け、第四回ポプラ社小説新人賞に応募。最終選考に選ばれた応募作「僕は普通にしゃべれない」を改稿した本作でデビュー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
149
当事者の苦しさは、おそらく書かれた内容だけにとどまらないだろう。吃音というハンディをテーマに描き、物語の世界にぐいぐいと引き込まれる。主人公の中学1年生・悠太をめぐる人々は、やさしくて理解のある人々も多いのだが、それでも苦しさは並大抵ではないことがわかる。姉や古部さん、立花先輩とは、理解してもらえないことに衝突するものの、自分自身にも気づきながら、成長していく。安易にまとまるようなテーマではないが、テーマの重さにつぶされないラストだった。2019/11/25
茜
126
この本を読んで私はひとつの答えを見つけました。以前に読んだ「吃音 伝えられないもどかしさ」で私は「言葉が出てくるのを待つか、それとも状況を見て出てくるであろう言葉をこちらから言った方が良いのだろうか?」という問題を自分で考えたんだけど、本書では言葉が出てくるのを待っている方が当事者には良いという事が書かれていました。主人公の悠太も周りの人達の優しさを知り一歩踏み出していきます。思わず頑張れっと応援している自分がいました。最後のサ行の言葉言える日も近いんじゃないかなぁと思いました^^2021/03/24
mocha
108
YA本。吃音に悩む少年の成長物語。日本では吃音は障害と認められていない。治療法も確立されていない。少年の台詞を読む時、その吃音を追うのがとてももどかしく胸が詰まるようだった。彼は口を開く度、ずっとずっとこんなに苦しいのか。からかい、同情、気味悪がったり普通にしろと非難したり…。知識がないせいで残酷になってしまう人達も悲しい。葛藤の先に感動のラスト。多くの子どもたちに読んでほしい。同じ苦しみを持つ著者だからこそ書けた話だと思う。2018/05/31
☆よいこ
94
YA。中学1年の最初のホームルーム、自己紹介が不安で柏崎悠太(かしわざきゆうた)は仮病で逃げた。吃音でしゃべれない、吃音を隠したい。悠太は逃げて隠した。姉に逃げちゃだめだと言われ、放送部に入った悠太はクラスメイトの古部さんと親しくなる。古部さんは他のクラスメイトとは距離を取るが、悠太と友達になってくれた。古部さんは悠太の吃音を「治す」という。二人でアニメの台本を読み練習するが、あまりのスパルタに悠太はいらだつ。「誰も僕の苦しみをわからない」姉とも喧嘩する▽僕はしゃべることが好きです▽良本2022/11/07
小木ハム
93
ティーンズ小説。吃音者は人にからかわれたり伝えられない惨めな気持ち以上に、将来に対しての不安と戦っている。自分が経営者なら、名前すら言えない人を雇いたいと思うか…。少なくとも喋る仕事は諦めるしかないんじゃないか…。どうして自分だけこんなにハンデを背負って、世界をせばめて生きていかなきゃいけないの?自暴自棄に陥る少年が、周囲の人の隠れた配慮や優しさに気づいていくお話。『与えられるばかりの人にはなりたくない。僕も誰かに、なにかを与えられる人間になりたい』という台詞は様々な逆境の立場にいる人へ刺さる言葉だ。2020/12/29
-
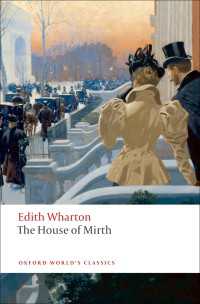
- 洋書電子書籍
- The House of Mirth




