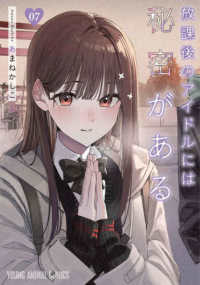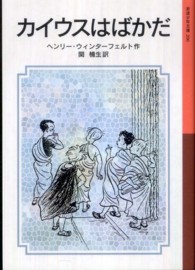内容説明
なぜ、フランスなのか?そして、絶望から立ち上がることができるのか。シャルリー・エブド襲撃事件、続けて起こったパリ同時多発テロで今なお衝撃と恐怖に支配される欧州。10年以上にわたりフランスを見続けてきた著者だからこそ、悲観的観測だけでなく、移民として懸命に生きる人々と市民たちの草の根の活動の中に希望を見出すことに成功した。
目次
第1章 フランス人、三代前はみな移民―人種の坩堝・パリ(移民たちと食べた無料のクスクス;常設の「派遣村」はアソシエーションの活動 ほか)
第2章 フランスの移民政策(テロの原因は移民への差別なのか;「世界の隠れ家」フランス ほか)
第3章 人生いろいろ、人種もいろいろ(私が出会った移民・難民たち;アフガニスタンから来た政治難民のマランガンさん ほか)
第4章 押し寄せる難民に揺れるヨーロッパ(移民大国ドイツの挑戦;ミュンヘンで市民の大歓迎を受ける難民・移民たち ほか)
著者等紹介
増田ユリヤ[マスダユリヤ]
1964年、神奈川県生まれ。国学院大学卒業。27年にわたり、高校で世界史・日本史・現代社会を教えながら、NHKラジオ・テレビのリポーターを務めた。日本テレビ「世界一受けたい授業」に歴史や地理の先生として出演のほか、現在テレビ朝日系列「グッド!モーニング」などコメンテーターとしても活躍。日本と世界のさまざまな問題の現場を幅広く取材・執筆している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fu
22
パリは洗練され華やかな街というイメージだが、2年前パリに行った時には以前に比べて雑然としている印象を受けた。パリの変容を感じていたところにパリ同時多発テロが起こった。本書前半は移民側への取材。不法に国境を越えることは生死をかけた命がけの行為であることがよくわかる。後半は移民政策に頭を悩ます受け入れ側を取材。フランスは移民を積極的に受け入れ、同化政策を行うことにより国を統治してきたが、失敗を認めざるを得なかった。ムスリムがキリスト教国に同化するのは容易ではない。テロの根底にあるのは宗教ではなく貧困。2016/09/10
サラダボウル
17
2015年11月パリ同時多発テロ。無差別であること、犯人がフランス国籍であり、難民を装って入国したことは、フランスと世界に衝撃を与えた。著者は現地で多くの人々を取材する。フランスは3代遡ればみんな移民だから、と市民も国も移民政策が手厚い。現在は反発勢力も大きいと思うが「(保護した)4割に裏切られたとしても、それでも目の前にいる子を助ける。それがフランス。」テロが移民のせいとは単純に言えない。10代半ばの少年たちの孤独で壮絶な逃亡には言葉を失う。若者にも読みやすい文章。移民とは?生きるとは?10代にもぜひ。2022/09/28
鯖
12
フランスが移民の国なんだなあと私が思ったのは、ジダンが花形だった頃のサッカーのフランス代表を見てからだなあ。その頃はイスラムの女子学生が学校でブルカを着用することの是非でもめていたように思うんだけど、…あの頃はまだ平和だったんだ…。リュックに現金を詰めてシリアから逃げてきた幼い兄弟や移民から労働大臣にまで上り詰めた女性等、さまざまな人々を取材してあった。2016/04/30
ののまる
10
「三代先は移民」と言われるフランスや、そのほかドイツの難民・移民対策。最近では「私はシャルリ」などのイメージが強かったので、フランスは予想に反して手厚かった。こういうの日本では全然無理っぽいな・・・(国民の多文化・多様性への認識・意識からして)。ミュンヘン駅に列車で到着した難民たちを拍手で迎えるドイツの人々。「週末ですし、何かできることはないかと思って」(子ども達と待っていた若いお父さん)「われわれは、1945年の出来事を決して忘れてはいない」(ドイツ人73歳男性)一方で排斥行動もある、共存の難しさ。2016/05/12
スプリント
10
難民騒動に揺れるヨーロッパで実際に現地で取材を行った著者による現状分析と未来への展望が書かれています。古来より難民(移民)があったヨーロッパと島国日本では事情も受け入れ基盤も違うので直接の参考には成り得ないと思いますが、難民の実情と受け入れる側が抱える問題点などは参考になると感じました。2016/04/02