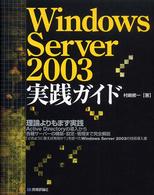内容説明
「今夜と明日の晩だけ―明後日になればきっと払えるからね」。簡易宿泊所の常連にして無銭飲食の常習者、ナルザワ先生の恬淡たる生き様(尾崎士郎『鳴沢先生』)。冬間近い北海道で出会った零落の旅役者一座に、同情の念を禁じ得ない私。自らの放浪体験に題材を取った長田幹彦の出世作(『零落』)。病床に臥せった故郷の老母に思いを残しつつ、男は遊興にふける。美しい春の風景が胸に沁みる(近松秋江『惜春の賦』)。浮浪、落魄、そして漂泊―仮の宿に人生を託した男たちの物語。
著者等紹介
尾崎士郎[オザキシロウ]
1898‐1964。愛知県生まれ。早稲田大学中退後、社会主義者として活動。大逆事件を題材にした作品で作家活動をはじめ、『人生劇場』で一躍人気作家となった
長田幹彦[ナガタミキヒコ]
1887‐1964。早稲田大学入学後、北海道を放浪。旅役者の生活を描いた『澪』で作家デビュー。その後も「祇園もの」の作品で人気を博し、作詞家としても活躍した
近松秋江[チカマツシュウコウ]
1876‐1944。岡山県生まれ。本名徳田浩司。東京専門学校(現・早稲田大学)在学中から新聞に評論を執筆。女性への執着を描いた作品によって、破滅型私小説の型を完成させた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新地学@児童書病発動中
120
こういう本を読むと、改めて百年文庫は素晴らしいシリーズだと思う。再読に耐えうる短編が収められており、文学の素晴らしさを実感する。この巻には宿をテーマにした三編を収録。尾崎士郎の「鳴沢先生」は最後の一行に凄みを感じた。長田幹彦の「零落」は絶品。旅役者たちと知り合いになった主人公の哀しみと自嘲が古風で端正な日本語で描かれている。こういう日本語を読むと、日本人で良かったとしみじみと思える。近松秋江の「惜春の賦」も素晴らしい。日本の古典の素養を感じる色彩豊かな文章で、この時期に読むと特に心に沁みる。2017/04/23
モモ
48
尾﨑士郎『鳴沢先生』私設簡易宿泊所の常連ナルザワ先生は帝大卒業生ながら無銭飲食の技をみがく日々。そしてむかえるあっけない結末。長田幹彦『零落』旅を続け、寂しくなってきた頃に知り合った旅役者の一座。一座と親しくなり、語られる彼らの人生の光と影が興味深い。近松秋江『惜春の賦』東京出身の春本と地方出身で老いた母を見舞う予定の牧野が旅に出た。東京を出発し、一人電車に乗って実家に向かうと、実家の現実がのしかかってくる感じは今も昔も同じなのだなと思った。京都の祇園の描写が美しい。今回は人生の「宿」といった感じの一冊。2023/02/25
神太郎
23
今回は全員日本人作家という事で一気読み。『鳴沢先生』は無銭飲食でやっていく鳴沢先生の話を面白おかしくしかし、ラストは何とも不思議な感じで終わらせる。今じゃこんなことは出来ないよなぁ~とか。『零落』はその意味の通り、落ちぶれた者達の話だ。人間くさい話で結構好きなジャンルだ。旅一座の淋しさなんかも感じる。『惜春の賦』は電報で老母が大変だってのに自分の旅を優先して楽しんでる男の話のせいかあまり主人公には良い印象がない。どんな状況でもそれなりに生きていける世の中だったのかもと今の方が生きづらい社会な気がする。2020/03/01
臨床心理士 いるかくん
20
3篇から成るアンソロジー。当ての無い旅で出会う旅一座と過ごす日々を描いた、長田幹彦の「零落」が個人的には好み。2014/02/17
鯖
19
尾崎士郎「鳴沢先生」無銭飲食と留置所を行き来する鳴沢先生。最期はポキンと折り曲げられ屑籠に。長田幹彦「零落」旅の一座を描いた一編。これをホワイトウォッシュしてきれいきれいすると伊豆の踊子になるんだと思う。近松秋江「惜春の譜」は死の迫った老母を見捨て、放蕩の旅を続ける息子の話。なんつうか小説家の無頼っぷりが存分に出てる3篇だなあと思った。全員近づきたくないやつ。2022/02/06
-
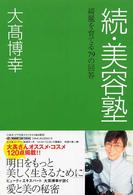
- 和書
- 美容塾 〈続〉