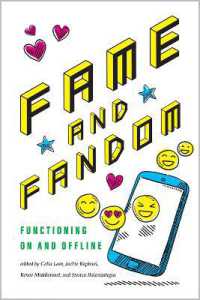内容説明
酒の名所、伏見の船宿に嫁いだのは登勢が十八の頃だった。頼りない夫と気難しい姑、打ち続く災厄にもへこたれずに生きぬく女性の輝き(織田作之助『螢』)。水上バスに乗って川岸の景色を眺めるうち、記憶の底から呼び出された「魔物」の正体(日影丈吉『吉備津の釜』)。都での宮仕えが決まった夫は津の川を東へ、妻は西へと別れた。ふたたび一緒に暮らせる日を願って妻は便りを待ち続けるが…(室生犀星『津の国人』)。暮らしに川が生きていた頃の、日本人の心の風景。
著者等紹介
織田作之助[オダサクノスケ]
1913‐1947。大阪生まれ。旧制第三高等学校時代より文学を志し、1940年、『夫婦善哉』で新進作家としての地位を獲得。坂口安吾、太宰治らとともに「無頼派」と呼ばれ、『わが町』『世相』『競馬』などを発表。人気作家として活躍したが33歳で死去
日影丈吉[ヒカゲジョウキチ]
1908‐1991。東京・深川生まれ。本名は片岡十一。アテネ・フランセでフランス語を学んだ後、フランス料理の指導をしていたが、戦後『かむなぎうた』が懸賞小説に入選して探偵小説作家に。翻訳家としても活躍した
室生犀星[ムロウサイセイ]
1889‐1962。石川・金沢生まれ。本名は照道。金沢地方裁判所に給仕として就職後、俳句や詩をつくり始め、20歳で詩人を志す。北原白秋主宰の「朱欒」に発表した詩で注目され、その後小説家としても認められた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新地学@児童書病発動中
100
川が物語の背景になっている3つの短編。織田作之助の『螢』は淀川の水の匂いが漂ってきそうなしっとりとした内容で、しっかり者のヒロインの生き様が心に残る。日影丈吉『吉備津の釜』はホラーと言っていい内容を持った小説。江戸川の水の流れが呼び起こす幻影に戦慄を覚えた。プロットの捻り方も見事だ。室生犀星『津の国人』はいつまでも夫の帰りを待ち続ける妻のけなげな心情が切ない。典雅な文体が小説の内容によく合っていた。3篇とも短編のお手本と言っていい物語で、改めて百年文庫の素晴らしさを実感。 2015/04/12
えみ
68
古くから人は水辺に暮らしを求めてきた。どんな時代も、いかなる状況下でも、流れがある限り人の生活に関わりを持って当たり前として存在してきた川。そこに感じる無常観。きっと古より刻み込まれてきた誰もが持つ故郷の風景を切り抜いてきた物語。3篇の短編を収録した『川』。百年文庫シリーズ第24弾。登勢の眩いばかりの強さの秘密が描かれた、織田作之助の『螢』。本当に恐ろしいものは記憶を便って不意に現れる、日影丈吉『吉備津の釜』。待ち人来ず揺れ動く心情が切ない、室生犀星の『津の国人』。様々な姿を見せてくれる人の面白さに感謝。2023/02/19
モモ
44
織田作之助『螢』登勢は潔癖症の夫、意地悪な姑とも明るく対峙する。不幸なことも諦めて受け入れる登勢。やがて奪われたような娘の代わりに養女にしたお良が坂本龍馬の妻になるエピソードに少し驚く。日影丈吉『吉備津の釜』事業が失敗し、自分を助けてくれる夢のような話に浮足立つも、思い出される祈祷師が話してくれた話。その話で救われる男の話。室生犀星『津の国人』切ない話。生活のために離れて暮らすことになった夫婦。便りがないまま何年も過ぎて…。這ってでも便りを書けば良かったのに。蛍の描写が美しく、人生に流れる川を感じる一冊。2022/09/03
鯖
21
オダサクの「蛍」がよかった。幸薄い登勢が嫁いだ先は川べりの宿、寺田屋。姑は気難しく、旦那は吃音の気があり神経質。いびられても、ぽやんとして芯の強い登勢はあんまり気にせず、黙々と宿を切り盛りしていく。「この世界の片隅に」のすずさんみたいな人だなあと思ってたら、突如西郷とか竜馬とか有馬さんの「おいごと刺せ」とか出てきて、アアアアアアこれ寺田屋じゃん気づかなかったよおおおおおと鼻息が荒くなる。すまん歴オタ失格じゃ…。いやなんか最近脳内イメージが銀魂のお登勢さんで定着してたもんで…。面白かったです。2019/05/01
マッキー
18
室生犀星の「津の国人」、なんて美しい言葉遣いなんだろう、と思ったね。筒井のしとやかで上品な佇まい、平安が舞台だからこそ映える。切ない結末になってしまったものの読後感は何とも満足感にあふれる。室生犀星これをきっかけにほかの作品も読んでみたくなった。2016/03/30