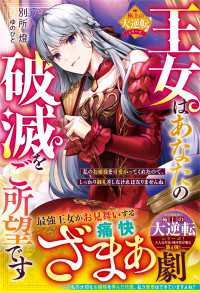内容説明
分子を生きたまま見る?南極に「空気の化石」がある?日本の薬がアフリカの感染症を治す?首長竜の新種と出会う?21世紀の科学を支える人たちはなにを見ているのか。『絶対音感』『青いバラ』『星新一』の著者が贈る、最新ノンフィクション。
目次
はじめに 自然という書物を読む人々
日本生まれの薬でアフリカ睡眠病に挑む―寄生虫学者・北潔と医師シュバイツァー伝
恐竜少女が首長竜の新種と出会う―古生物学者・佐藤たまきと数学者・藤原正彦の青春記
世界の乾燥地で植物生産の向上を目指す―農業気象学者・坪充と反アパルトヘイト運動の闘士ネルソン・マンデラ伝
地震国日本から世界に発信する―地震学者・石田瑞穂と国語学者・大槻文彦伝
南極の「空気の化石」に地球の歴史を見る―物理学者・深澤倫子と雪博士・中谷宇吉郎の研究生活
言葉の不思議を探究する―音声工学者・峯松信明と動物科学者テンプル・グランディンの自閉症報告
ウイルス感染症のメカニズムに迫る―ウイルス学者・甲斐知恵子と物理学者マリー・キュリー伝
「空飛ぶ化学工場」黄砂を日本と中国で観測する―物理学者・岩坂泰信と探検家・大谷光瑞伝
人間とコンピュータの対話をデザインする―情報科学者・中小路久美代と作曲家モーツァルト伝
顕微鏡を覗いて生命の本質を探究する―生物物理学者・徳永万喜洋と発明家トーマス・エジソン伝
地球から宇宙船を操縦する―宇宙科学者矢野創と宇宙飛行士エリスン・オニヅカ伝
アルツハイマー病の解明に挑む―脳神経科学者星美奈子と霊長類学者ジェーン・グドール伝
おわりに 師と弟子
著者等紹介
最相葉月[サイショウハズキ]
1963年、東京生まれの神戸育ち。関西学院大学法学部卒業。科学技術と人間の関係性、スポーツ、教育などをテーマに執筆。97年、『絶対音感』で小学館ノンフィクション大賞受賞。07年、『星新一 一〇〇一話をつくった人』で大佛次郎賞、講談社ノンフィクション賞、日本SF大賞、08年、同書で日本推理作家協会賞、星雲賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。