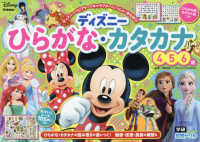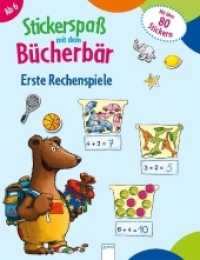内容説明
「差別的表現」と「ヘイト・スピーチ」は同列に扱ってよいのか?ヘイト・スピーチ規制の法的可能性を理性的・公共的に問う。
目次
第1部 日本におけるヘイト・スピーチ(ヘイト・スピーチとレイシズムの関係性―なぜ、今それを問わねばならないのか;新保守運動とヘイト・スピーチ;ヘイト・スピーチとその被害)
第2部 表現の自由とヘイト・スピーチ(表現の自由とは何か―或いはヘイト・スピーチについて;表現の自由の限界;言論規制消極論の意義と課題)
第3部 ヘイト・スピーチに対する刑事規制(刑法における表現の自由の限界―ヘイト・スピーチの明確性と歴史性との関係;名誉に対する罪によるヘイト・スピーチ規制の可能性―ヘイト・スピーチの構造性を問うべき次元;ヘイト・スピーチ規制の意義と特殊性;ヘイト・スピーチに対する処罰の可能性)
著者等紹介
金尚均[キムサンギュン]
1967年生。立命館大学大学院法学研究科博士後期課程中退。現在、龍谷大学大学院法務研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Sakana
7
本書では、ジャーナリスト、社会学者、憲法学者、刑法学者といった様々な地点からヘイトスピーチについて多角的に論じられている。それは日本の現状、日本やアメリカの規制消極論、ドイツの民衆扇動法であったりと様々である。しかし、通徹しているのは「ヘイトスピーチは悪である」という前提から出発するという点である。そこから規制することはどうなのか、憲法的に許されるのかが問われなくてはならない。本書はその実践であると同時に、様々な構成の議論を各々が展開することによって、本書それ自体が公的な討論の場になっている。刺激的な一冊2015/11/29
凜
5
感情論としてヘイトスピーチは自由が保障されるべき表現の形ではないと思うけれど、きちんと憲法に照らして考えていけば難しい問題なのだな、と。しかし、憲法とは人権を守るためにあるのではないのか?人権侵害を規制する足枷になっているのはどうかと思う。個別のケースでもっと柔軟に対応していくべきではないかと思う。2019/07/03
わたなべ
0
答えは簡単には出ないね2016/01/24
Kaori Sato
0
「…ここでの議論は、差別的表現がいいとか悪いとかの問題ではないということです。差別的表現が悪いのは当然であるとしても、それを法的に規制することがいいかどうか…」ヘイトスピーチがどんなにおぞましくてクソでも、一度でも法律を学んだことがある者なら、表現規制との兼ね合いを無視するとこはできない。それへの回答が欲しくて読んだけれど、やはり問題はそう簡単ではなく、共著者の誰もが程度の差はあれ逡巡している。一番しっくりきたのは、「何がヘイトスピーチに該当し、そのヘイトスピーチが何をもたらしうるかは、当該国家社会の歴史2015/08/26
お魚くわえたザサエさん
0
どのような規制をすると、大衆運動にどのような影響があるのかを細かく示している。専門書なので値段も高く読むには法律の知識が無いと理解するのは難しいが、ヘイトスピーチに対し法律や政策でどうしていけばよいかについて自分の意見を持つためには欠かせない本。2014/12/30
-
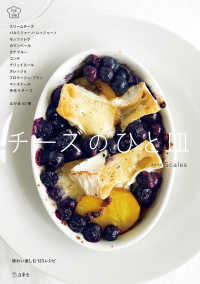
- 電子書籍
- チーズのひと皿 料理の本棚 立東舎