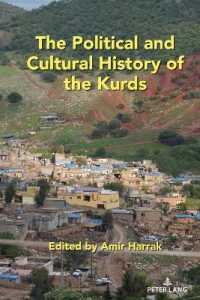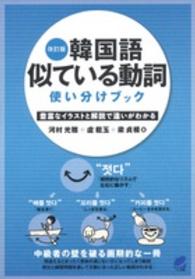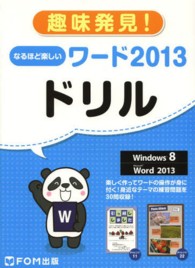出版社内容情報
有史以来の外来文化受容(翻訳)のあり方が「秘すれば花」の伝統文化を生み出し,〈秘〉の思想が今日まで日本文化の核をなしてきたとする斬新な日本翻訳文化論。
内容説明
有史以来連綿としてつづけられてきた翻訳=外来文化受容のあり方が「秘すれば花」の伝統文化を生み出し、“秘”の思想が今日に至るまで日本人の思考の核をなして継承されてきたとする斬新な視覚からの日本翻訳文化論。
目次
第1章 秘の思想
第2章 出会い
第3章 オモテ・ウラの文化
第4章 秘の文化の起源―漢字
第5章 言霊とはなにか
第6章 古代大和の翻訳語
第7章 密教
第8章 キリシタンという「秘」
第9章 カースト制差別
第10章 翻訳文化としての天皇制
著者等紹介
柳父章[ヤナブアキラ]
1928年東京生まれ、東京大学教養学科卒業。翻訳論・比較文化論専攻
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
2
ふむ2024/06/11
もちねこLv.4
0
地理的な外部からやってきた外国語との「出会い」によって生まれる「翻訳の体験」。翻訳においては、取り込みきれない意味が無意識化され、それは覆い隠されてしまう、それがすなわち「秘」として機能する。また翻訳語においてはいわゆる「差異」とは違い、あらかじめ「価値判断」が含まれるという。筆者は世阿弥の「秘事というふことを顕はせば、させる事にてもなきものなり」という美的価値観が日本文化の核心だとして、「翻訳文化論」と絡めて上のよな論を展開する。2015/05/21