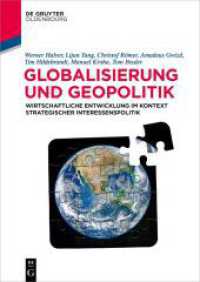出版社内容情報
明治政府は近代化の象徴として洋装を推奨したが、とくに女性のあいだでなかなか普及しなかった。それが大正末期から昭和にかけて、高等女学校のセーラー服として一気に拡がりをみせる。セーラー服の制服が生まれて百年。なぜ女学生たちはセーラー服にあこがれたのか。本書は、全国すべての高等女学校を調査した集大成。図版約100点、「全国高等女学校の洋式制服一覧」を付す。
内容説明
全都道府県のほぼすべての高等女学校がセーラー服を制服にしたのはなぜなのか。各校の記念誌など膨大な史料をもとに、その特色や地域性、女学生たちの喜びや不満を活写する。写真100点、全国高等女学校の洋式制服一覧を付す。
目次
序章 魅力的なセーラー服
第1章 体操服と改良服
第2章 服育としての効果
第3章 セーラー服の三都と三港
第4章 セーラー服に統一を図った県
第5章 洋式の制服の統一を嫌う県と制定が遅れる県
第6章 全国のセーラー服の状況と個性
第7章 個性の強いミッション系
第8章 日中戦争とアジア・太平洋戦争下のセーラー服
終章 セーラー服が誕生した意味
著者等紹介
刑部芳則[オサカベヨシノリ]
1977年東京都生まれ。中央大学大学院博士後期課程修了。博士(史学)。中央大学文学部日本史学専攻兼任講師を経て、日本大学商学部准教授。専門は日本近代史。『明治国家の服制と華族』(吉川弘文館、2012年)で日本風俗史学会江馬賞受賞。ほか著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
崩紫サロメ
kenitirokikuti
ぷてらん
元気伊勢子
horuso